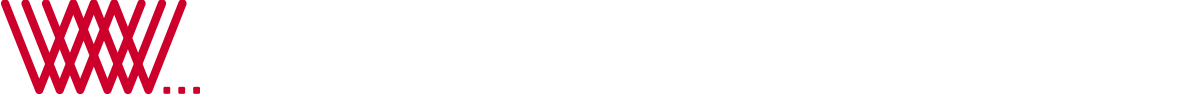「おすすめの消費者金融はどれ?」
「審査甘い消費者金融ランキングが知りたい」
結論、審査が甘い消費者金融はありません。
消費者金融は貸金業法に基づいて運営されており、審査が慎重に行われるため審査が甘いとは言えません。

審査が甘くないが消費者金融は安心
- 審査の待ち時間が不安でも安心
事前診断で借入可否がわかる - 審査が不安でも安心
大手だと審査通過率を公開している借入先あり - 周りにバレにくくて安心
原則在籍確認の電話・郵送物なし
中でも、プロミスは約3人に1人※が審査に通過していて審査に期待が持てる借入先です。
簡単な質問に答えるだけでお借入可能か分かるパパっと一秒診断があるので、審査が不安な方は申込み前に試してみて下さい。
おすすめPOINT!
- 初めての利用なら30日間利息0円!
- 即日融資・最短3分で審査可能!
- 24時間・土日もWEB申し込み可能!
金融庁に一覧登録されている消費者金融の数は264社あります。
以下診断では、自分の条件に合った消費者金融を調べられるので、ぜひ試してみて下さい。
あなたにぴったりの消費者金融は?
 審査が通るかどうか
審査が通るかどうか
 審査結果が出るまでの
審査結果が出るまでの待ち時間が長くないか
 審査を受けることが
審査を受けることが周りにバレないか
返済できるか
 来店不要でスマホ
来店不要でスマホ1本で借入できるか
 収入証明書不要で
収入証明書不要で手続き可能か
この記事では審査甘い消費者金融がない理由や大手と中小の消費者金融について解説します。
併せてカードローンについても紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
審査甘いって本当?消費者金融ランキング
この記事で分かること
- 審査甘い消費者金融はない
- 大手消費者金融は審査を安心して受けるための仕組みが充実
- プロミスは審査通過率が35.6%※と約3人に1人の割合で借入可能
- 自分にあった消費者金融の選び方
目次
- 1 審査が甘い消費者金融がないのは返済能力の調査が義務付けられているから
- 2 大手消費者金融おすすめランキング5選!即日融資や借入先について解説
- 3 中小消費者金融おすすめランキング10選!大手との審査基準の違いについても解説
- 3.1 フタバなら最大金利17.95%で借入できる
- 3.2 アローはアプリから申し込めて最短45分で審査が完了
- 3.3 ダイレクトワンは初めて契約する方なら55日間利息0円で利用できる
- 3.4 フクホーは来店で即日融資可能で大阪在住の方におすすめの消費者金融
- 3.5 アムザは年金受給者の方でも消費者金融に申し込むことが可能
- 3.6 ベルーナノーティスは14日間無利息で何度でも利用できる
- 3.7 セントラルは平日14時までの申込で即日融資に対応可能
- 3.8 ティー・アンド・エスは2回目以降なら電話・WEBでの即日融資にも対応できる
- 3.9 ユニーファイナンスはFITカードを使うとプロミスATMで借入・返済が可能
- 3.10 ハローハッピーは他社の消費者金融で借入がまだ残っている方でも申込可能
- 4 信販会社のカードローンおすすめランキング3選!独自のサービスや特徴についても解説
- 5 キャッシュレス決済型ローンのおすすめランキング!アプリで完結可能な2つについて解説
- 6 消費者金融の申込時の選び方4つ
- 7 「消費者金融」とは国から認可された貸金業者のこと
- 8 消費者金融カードローンは銀行カードローンより審査が甘い?法律や金利から比較
- 9 消費者金融の審査を通過して即日融資を受けるための注意点
- 10 消費者金融の審査に落ちた人の3つの理由
- 11 消費者金融は一度でも借りると危険?やばい業者を回避するために注意すべき3つのポイント
- 12 職業や属性ごとにおすすめの消費者金融を一覧で解説!
- 13 審査が甘い消費者金融についてよくある質問
- 14 お金を借りたいなら消費者金融がおすすめ!審査は甘くないが安全に借りられる
審査が甘い消費者金融がないのは返済能力の調査が義務付けられているから
 消費者金融は、貸金業法において利用者の返済能力を厳格に調査することが義務付けられています。
消費者金融は、貸金業法において利用者の返済能力を厳格に調査することが義務付けられています。
これは貸し倒れを防ぐためだけでなく、消費者の過剰な借入による多重債務を抑制することも目的としています。
(返済能力の調査)
第十三条 貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。
もしこの返済能力を確認する審査の過程を満たさなかった場合、業者は法律違反として行政処分の対象となってしまいます。
このような事態を未然に防ぐため、信用情報機関(CICやJICC)を通じて、申込者の他の借入状況や返済履歴は詳細にチェックされます。
正規の消費者金融は慎重に審査が行われるため、「審査が甘い」という表現を使いません。
そのため、「審査甘い」と謳う貸金業者は闇金の可能性があるため絶対に借りないようにしましょう。
審査が甘くなくても大丈夫!
審査に通るか心配な方は審査通過率を公表している借入先だと審査に安心して挑むことが出来ます。
また、以下の消費者金融は審査の前に借入可否の確認ができる事前診断がありますので気になる方は試してみて下さい。
プロミスは審査通過率が35.6%!
\約3人に1人は審査に通過◎/
【ドラッグすると左右にスクロールできます】
| 消費者金融 | おすすめポイント | 審査通過率 (2025年1月時点) |
融資時間※ | 無利息期間 |
|---|---|---|---|---|
プロミス |
最短3分※で審査が完了! 約3人に1人が審査通過! 1秒パパッと診断を試す |
〇 35.6% |
最短3分 | 初回30日間※2 |
レイク |
無利息期間が 365日*! 365日間利息*0円で借りてみる |
ー 非公開 |
最短15分※3 | 365日* |
アコム |
3秒スピード診断で 事前に借入可否がわかる! 3秒スピード診断を試す |
◯ 39.6% |
最短20分※1 | 初回30日間 |
注釈・参考
※:申込時間や審査状況によりご希望に添えない場合がございます。また、受付時間や一部金融機関の営業時間によっては、振り込みが翌営業日以降となる場合があります。
*※無利息について:
■365日間無利息
・初めてのご契約
・Webでお申込み・ご契約、ご契約額が50万円以上(お借入れ額1万円でも可能)で
ご契約後59日以内に収入証明書類の提出とレイクでの登録が完了の方
■60日間無利息:初めてのご契約。
Webお申込み、ご契約額が50万円未満の方。
・無利息期間経過後は通常金利適用
・初回契約翌日から無利息適用
・他の無利息商品との併用
※1:お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※2:メアド登録とWeb明細利用
※3:Webで最短15分融資も可能、21時(日曜日は18時)までのご契約手続き完了(審査・必要書類の確認含む)で、当日中にお振込みが可能です。
※4:無担保キャッシングローン利用時
※5:お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。
参照:アコム|マンスリーレポート(2025年3月期下期)
参照:プロミス|月次データ(2024年3月期2月)
参照:アイフル|月次データ(2025年3月期)
審査が甘いと返済を延滞する人が増え返済されないリスクがある
前項でも述べたように、審査が甘いということは返済能力が十分でない人々への貸付が増え、結果として返済の延滞や貸倒れのリスクが高まることを意味します。
特に年収に見合わない過剰な借入は、返済不能に直結しやすいです。
実際バブル崩壊後の日本では多くの金融機関が不良債権問題に直面し、大規模な経済混乱を引き起こしました。
我が国銀行の不良債権残高を、全国銀行の「リスク管理債権」残高でみると、バブル崩壊後の93年3月期以降増加傾向を続けている。
この経済への影響を受け、貸付における厳格な審査が不可欠であることが広く認識されることになりました。
その後2000年代前半には大量に多重債務者が生み出され、消費者金融業界全体で貸倒れが増加し、多くの業者が倒産や業務縮小に追い込まれました。
結果的に政府は2006年に改正貸金業法を導入し総量規制を施行しました。
これらの背景から審査が甘いことは延滞などの返済に対するリスクが増えるだけでなく、経済全体に影響を与えることから金融機関が表現として用いることはありません。
借入の際は、必ず返せるという返済の目途を立ててから申し込むようにしましょう。
大手消費者金融おすすめランキング5選!即日融資や借入先について解説

大手消費者金融は【貸金業法】【利息制限法】【出資法】に則り運営している貸金業者です。
法律に基づいた適正な審査を行っており、審査は甘いとはいえません。
消費者金融の審査が安心な理由
- 審査の待ち時間も安心
融資時間が早くて審査結果が出るまでの不安解消 - 審査が不安でも安心
大手だと審査通過率を公開している借入先あり - 周りにバレにくくて安心
原則在籍確認の電話・郵送物なし
消費者金融では審査を安心して受けることができる仕組みが整っています。
それでも審査が不安な方は、審査通過率を公表している消費者金融を選ぶとよいでしょう。
中でも、プロミスは約3人に1人※1が審査に通過していて審査に期待が持てる借入先です。
以下の一覧では金利・審査の通りやすさ・融資時間などの特徴を比較していますので、自身に合った借入先を見つけて下さい。
プロミスは約3人に1人※1が審査通過!
\審査が不安でも期待が持てる◎/
【ドラッグすると左右にスクロールできます】
| 消費者金融 | おすすめポイント | 審査通過率 | 審査スピード | 上限金利 | 無利息期間 | 電話連絡 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロミス |
審査通過率が高く 周りにもバレにくいから 契約数が多い! 詳細はこちら |
◎ 35.6%※1 |
◎ 最短3分※ |
◎ 18.0% |
最大30日間 | 原則なし | 1~800万円 |
レイク |
365日間*は利息0円 詳細はこちら |
非公開 | 申込後 最短15秒 融資は最短15分※a |
〇 年18.0%※c |
365日間※ | なし※b | 1~500万円 |
アコム |
最大30日間は 利息0円で借入可能 詳細はこちら |
〇 39.6%※2 |
◎ 最短20分※d |
〇 年2.4%~17.9% |
最大30日間 | 原則、お勤め先へ 在籍確認の電話なし※e |
1万円~800万 |
SMBCモビット |
原則電話・郵便物なしで 会社・家族にバレにくい 詳細はこちら |
ー 非公開 |
◎ 最短15分 |
〇 18.0% |
なし | 原則なし | 800万円 |
| アイフル | 最短18分で借入可能 |
34.5※3 | 最短18分※ | 18.0% | 初めての方は 最大30日間 |
原則なし | 1万円~800万 |
SMBCグループプロミス
原則、職場への在籍確認の電話なし
| バレにくさ | 即日融資 | 利息 |
|---|---|---|
 職場や自宅への 原則電話・郵送なし |
 最短3分 融資可能 |
 初回利用 30日間利息0円 |
おすすめのポイント
- 1秒スピード診断で借入可能か確認できる
- 原則電話連絡・郵送物なし
- 24時間いつでも最短10秒で振込
それぞれの消費者金融の特徴をよく理解しながら、自身の目的・返済プランに合った消費者金融を探してみましょう。
ここでは、お金借りる際に消費者金融がもつ特徴について詳しく解説します。
注釈・参照
※無利息について:
■365日間無利息
・初めてのご契約
・Webでお申込み・ご契約、ご契約額が50万円以上(お借入れ額1万円でも可能)で
ご契約後59日以内に収入証明書類の提出とレイクでの登録が完了の方
■60日間無利息:初めてのご契約。
Webお申込み、ご契約額が50万円未満の方。
・無利息期間経過後は通常金利適用
・初回契約翌日から無利息適用
・他の無利息商品との併用
※申込状況によってはご希望に添いかねます。
※お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※a 21時(日曜日は18時)までのご契約手続き完了(審査・必要書類の確認含む)で、当日中にお振込みが可能です。一部金融機関および、メンテナンス時間等を除きます。
※b 在籍確認が必要な場合でも、お客さまの同意なくお電話いたしません。
※c 貸付利率はご契約額およびご利用残高に応じて異なります。
※d お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※e 電話での確認はせずに書面やご申告内容での確認を実施
※1SMBCコンシューマーファイナンス月次レポート
※2アコムマンスリーレポート
※3アイフル月次レポート
※4参照:貸金業法の改正について 総量規制の導入
プロミスは大手消費者金融の中でも審査通過率が高いため契約者数が多い

プロミスは無利息期間が初回借入日の翌日から30日間あり、返済時の利息を安く抑えたい方におすすめです。
借入しなければ特典が開始されることはありませんので、自身の借入のタイミングでお得に利用することが出来ます。
また、プロミスは最短3分※1融資可能な消費者金融で、審査通過率・成約率にも定評がある消費者金融です。

プロミスとアイフルを2024年の6月~8月の審査通過率※2を比較した以下の結果は下記の通りです。
| 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|
| プロミス | 35.70% | 36.0% | 36.2% |
| アイフル | 32.5% | 33.0% | 30.5% |
プロミスはアイフルに比べて3カ月連続で審査通過率が高く、約3人に1人の割合で借入をすることが可能です。
そのため、審査をするうえで、申込者の返済能力を判断する基準である以下3点を事前に確認しておきましょう。
借入の際に確信しておくこと
- 安定した収入があるか
- 信用情報に傷がついていないか
- 他社借入がないか
上記の3点を全て満たしている人は基本的に消費者金融での借入が可能です。
もし、満たしていない項目があるなら借入が難しくなる可能性があるので、借入先に相談するようにしましょう。
三井住友銀行ATMで借入・返済などの手続きを行う際は、利用手数料も無料になる特徴もあります。
まずは1秒パパっと診断を試す
| プロミスの基本情報 | |
|---|---|
| 融資スピード | 最短3分 |
| 審査通過率※2 | 35.6% |
| 金利 | 2.5%~18.0% |
| 事前審査 | なし |
| 無利息期間 | 最大30日間 |
| 申込条件 | 年齢18歳以上74歳以下で安定した収入がある方※4 (パート・アルバイトなどによる安定した収入があれば、主婦や学生の方でも申し込み可能) |
| 必要書類 | 本人確認書類、収入証明書 |
注釈
※1:お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※2:審査通過率の参考
SMBCコンシューマーファイナンス月次レポート
アイフル月次レポート
※3:メールアドレス登録とWeb明細利用の登録が必要です
※4:お申込時の年齢が18歳および19歳の場合は、収入証明書類のご提出が必須となります。
高校生(定時制高校生および高等専門学校生も含む)はお申込いただけません。
収入が年金のみの方はお申込いただけません。
■プロミスの総評
プロミスは初めてカードローンを利用する方におすすめの消費者金融です。
本審査の時間も最短3分※1で行うことができ、スムーズにお金を借りられます。
さらに、アプリローンを利用すれば、カードなしで借入も返済も行うことが可能です。
アプリの利用や毎月の返済で、景品交換や買い物時に使えるポイントも貯められます。
気になることがあればアプリで確認もできるので、困った時にサポートしてもらえる安心感もあります。
消費者金融が初めての方にとっては利用しやすいカードローンといえるでしょう。
- プロミスの審査の甘さに関する
利用者の声① - プロミスの審査の甘さに関する
利用者の声② - プロミスの審査の甘さに関する
利用者の声③
| 審査から借入までスムーズ! | 女性(アルバイト・パート)45歳~49歳 |
|---|---|
| 総合的な満足度 | おおむね満足です |
| 借入までの早さ | 審査から借入までとてもスムーズでした。 1日くらいで完了でした。 |
| 金利の低さ | 決して低くは無いです。 |
| 借入時の便利さ | アプリで申込2分ほどで振り込まれます。 |
| 必要な時にすぐ借りれた! | 男性(正社員)40歳~44歳 |
|---|---|
| 総合的な満足度 | 即日融資が可能で 必要な時にすぐ借りられて助かりました。 |
| 借入までの早さ | 早いです。数時間だったと思います。 |
| 金利の低さ | 返しやすい低さで、助かりました。 |
| 借入時の便利さ | ATMで借入出来、誰にも見られないので助かりました。 返済もATMや、ATMが時間外だとWEB返済できて、かなり便利です。 |
| アプリも使いやすかった! | 男性(正社員)25歳~29歳 |
|---|---|
| 総合的な満足度 | 即日融資が可能で 必要な時にすぐ借りられて助かりました。 |
| 借入時の便利さ | ATMで借入出来、誰にも見られないので助かりました。 |
| 金利の低さ | 返済もATMや、ATMが時間外だとWEB返済できて、かなり便利です。 |
レイクは初めての方なら365日間*金利0円で利用できる

レイクがおすすめな人
- Webで最短15分※2で借入したい人
- 長い無利息期間で安心して返済したい人
- ローンカードなしで取引したい人
レイクは他の消費者金融と異なり、365日間の無利息期間*を設けています。
Web申込限定で、契約額に応じて無利息期間が変わります。
提供されている金利特典の種類は、以下の通りになります。

※無利息期間経過後は通常金利適用
※初回契約翌日から無利息適用
※他の無利息商品との併用不可
また、主な消費者金融の特典期間は以下の通りです。
| カードローン名 | 最大の特典期間 |
|---|---|
| プロミス | 30日間 |
| アイフル | 30日間 |
| レイク | 365日間* |
| SMBCモビット | なし |
| セントラル | 30日間 |
ローン返済時の利息をなるべく安く抑えたい方におすすめなカードローンです。
ただし金利特典の影響からか、収益は若干減少してきています。
2024年4月~2024年12月までの獲得収益は、以下の通りです。
参考元:SBI新生銀行 四半期決算情報
個人向け無担保ローンの利息収益が減少したことで、営業収益は230億6,400万円低下しています。
経常利益も、前年度に比べて179億300万円の減少です。
ただし現状サービスへの影響はなく、借入額の制限等も行われていません。
利用者数を徐々に増やすことができれば、以前と同等の収益状況まで改善される可能性が高いです。
レイクは365日間*の無利息期間で利息を抑えられるので返済の不安がある人におすすめです。
まずは1秒診断を試す
| レイクの基本情報 | |
|---|---|
| 実績※1 | 営業収益:2,757億円以上 |
| 審査時間 | 申込後最短15秒 |
| 融資スピード※2 | Webで最短15分融資も可能 |
| 金利 | 年4.5%~18.0%※3 |
| 申込条件 | 20歳以上~70歳 |
| 必要書類 | 本人確認書類、収入証明書 |
■レイクの総評
レイクは、返済時の利息をなるべく節約したい方におすすめな消費者金融です。
用途や返済プランに合わせて金利特典を選ぶことで、返済時の利息を最小限に抑えられます。
金利特典をうまく活用すれば、365日間まで特典期間を維持することが可能です。
またレイクはWEB申込を利用すれば、webで最短15分※で融資を受け取れます。
21時までに契約完了すると融資を銀行口座へ直接送金できるため、急な出費が発生した時などに便利です。
レイクアプリのスマホATM取引を使う場合、ローンカードの発行は必要ありません。
金利特典が長くてカードレス取引も可能なカードローンを探している方は、ぜひ申込を検討してみてください。
- レイクの審査の甘さに関する
利用者の声① - レイクの審査の甘さに関する
利用者の声② - レイクの審査の甘さに関する
利用者の声③
| 確認作業は時間がかかった | 男性(正社員)50歳~54歳 |
|---|---|
| 感想 | やもなく借入することになった。 早かったが思っていたより確認作業が面倒だった記憶があります。 毎月返済しないといけないが、近くに店舗がないので返済がとても不便だった。 もう少し便利な場所にあればと思いました。 |
| 少額から借りられた | 女性(正社員)30歳~34歳 |
|---|---|
| 感想 | 審査までの時間が短く、借入がスムーズに行えました。 少額から借りれるのでよかったです。 |
| 無人機の利用が便利 | 男性(正社員)50歳~54歳 |
|---|---|
| 総合的な満足度 | まだ平成初期の頃にATM形式の無人機で借入をしました。 審査は割と早く、無人機前で待っているとしばらくして審査通って借入できました。 その後何度か利用しましたが、毎回カードを利用して借入をしました。 |
注釈
※1:2021年4月~2022年3月の1年間のデータ
※2:21時(日曜日は18時)までのご契約手続きを完了(審査・必要書類の確認含む)で、当日中にお振込みが可能です。一部金融機関および、メンテナンス時間等を除きます。
※3:貸付利率はご契約額及びご利用残高に応じて異なります
■365日間無利息
・初めてのご契約
・Webでお申込み・ご契約、ご契約額が50万円以上(お借入れ額1万円でも可能)で
ご契約後59日以内に収入証明書類の提出とレイクでの登録が完了の方
アコムは最短20分で審査が完了し審査通過率も高め

アコムは3秒診断による簡易診断サービスが用意されているため、事前に借入可能かがすぐに分かります。
また1936年から貸金業を行っている歴史ある消費者金融のため、安心して利用できる借入先です。
サイト内に年齢・年収・他社での借入状況などを入力すれば、最短3秒で融資の可否を確認できます。
3秒診断はシミュレーションの一種であるため、利用しても信用情報に申込履歴が残ることはありません。
診断結果を確認した後に申込すれば、ある程度審査を有利に進められます。
「審査落ちが心配だから、まずは診断で借入できるかどうかを確認したい」という方におすすめです。
さらに、診断後にそのまま申込を行うと、最短20分※1で融資を受け取ることも可能です。
急いで借りたい人にも対応している消費者金融といえるでしょう。
また初めての方なら契約日の翌日から最大30日間利息が0円で借入ができるため、金利を抑えてお金を借りたい方におすすめです。

無利息期間のない消費者金融で10万円借入した時とアコムの無利息期間を使用した際の金利の差は下記の通りです。
| アコム (30日無利息) |
SMBCモビット (無利息期間なし) |
|
|---|---|---|
| 最低返済額 (32回払い) |
4,057円 | 4,000円 |
| 合計利息 (32回払い) |
25,767円 | 26,260円 |
| 総支払額 (32回払い) |
125,767円 | 126,260円 |
アコムは借入の翌日から30日間利息が無料になるため、SMBCモビットに比べて約1か月間利息を払う必要がありません。
そのため支払う利息が低くなり、結果的に総支払額も抑えられます。
アコムは24時間最短10秒で振込※3を受けられるため、今すぐ借入を行いたい人におすすめの消費者金融といえます。
アコムのキャッシングカードは、クレジット機能が付いたキャッシングとショッピングの両方で利用できる便利なカードです。
複数のカードを使い分けることが苦手な人やカードは1枚で管理したい人にはぴったりのカードといえるでしょう。
さらに、アコムは審査通過率が42.4%※2で約2.5人に1人が審査通過しています。
「はじめてのアコム」というように一社目のカードローンに選ばれることが多いので審査通過率が高いようです。
3秒スピード診断を試す
| アコムの基本情報 | |
|---|---|
| 融資スピード | 最短20分※ |
| 審査通過率※2 | 39.6% |
| 金利 | 年2.4%~17.9% |
| 事前審査 | 3秒スピード診断あり |
| 無利息期間 | 最大30日間 (はじめての借入の場合) |
| 申込条件 | 20歳以上で返済能力がある方 |
| 必要書類 | 本人確認書類、収入証明書 |
注釈
※1お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※2参照データ:アコムマンスリーレポート
※3金融機関により異なります。
■アコムの総評
アコムは、申込前に審査を無事通過できるか確認しておきたい方におすすめな消費者金融です。
簡易診断を利用すれば、その場で事前に借入できるかどうか結果を確認できます。
診断後にそのまま申込を行うと、最短20分※で融資を受け取ることも可能です。
またアコムは、ネットバンキングを使った取引にも対応しています。
スマホ・PCで金融機関口座を登録しておけば、わざわざ銀行・提携コンビニのATMへ行く必要はありません。
日時に関係なく、いつでもネット上・アプリで取引が行えます。
申込から借入までの手続きをなるべく短時間で完結させたい方は、ぜひ申込を検討してみてください。
※お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
- アコムの審査の甘さに関する
利用者の声① - アコムの審査の甘さに関する
利用者の声② - アコムの審査の甘さに関する
利用者の声③
| 借入のスピードと審査の優しさを感じた | 男性(正社員)30歳~34歳 |
|---|---|
| 感想 | 借入で振込にするとほんとうにはやかったとおもう。 そして審査もはじめてかりたときのイメージはとても優遇してくれていた気がするので世間には優しいさいていげんの審査をしてるんだと感じた。 |
| 自動契約機(むじんくん)で借入できた | 男性(正社員)50歳~54歳 |
|---|---|
| 感想 | ギャンブルにハマっているときに無人で、借入出来るので借りてしまった。返済しても又パチンコで負け借りてしまう。50万までは早かったです。 借りるのは簡単でしただが、返すのは大変でした。 |
| 安心感とスピードで選んだ | 男性(正社員)40歳~44歳 |
|---|---|
| 感想 | 急遽お金が必要になり借入しました。すぐに借りられて返済もスムーズだったので問題はなかったです。 他の会社も考えましたが、良く耳にする企業名だったし、CMでも良く目にしていたので、多少は安心な所で思い御社で借入る事になりました。 |
SMBCモビットは無料の事前審査ができて申込からの手続きがWeb完結

SMBCモビットは家族や職場に内緒で借りたい時に便利なWEB完結申込に対応している消費者金融です。
申込から融資・返済まですべてWEB完結することが出来ます。
WEB完結申込を利用すれば、職場への電話連絡原則なしでカードローンを契約することが可能なため、職場の同僚や家族にバレる可能性が低くなります。

SMBCモビットのWEB完結申込がおすすめな理由は以下の4つです。
SMBCモビットのWEB完結がおすすめな理由
- 来店なし
- 書類提出なし
- 電話連絡原則なし
- 郵送物なし
SMBCモビットは来店や書類提出などが原則ないため、こっそり借入をしたい人も安心して利用することができます。
また、借入や返済も場所を問わずいつでもどこでもスマホでかんたんに取引が可能です。
無料で事前に借入可能がどうか診断できる10秒簡易審査もありますので、気になる人は予め試してみて下さい。
SMBCモビットは、三井住友銀行ATMで取引する際の手数料が0円です。
コンビニATMは利用時に手数料が別途かかりますが、三井住友銀行なら余計な手数料を払う必要はありません。
ATMで頻繁に借入・返済を行うことが多い方にとっては、有益なサービスといえます。
まずは10秒簡易審査を試す
| SMBCモビットの基本情報 | |
|---|---|
| 融資スピード | 最短15分 |
| 審査通過率 | 非公開 |
| 金利 | 3.0%〜18.0% |
| 事前審査 | 最短10秒 |
| 無利息期間 | なし |
| 申込条件 | ・20歳以上74歳以下で安定した収入のある方 (アルバイト、パート、自営業の方も利用可能) ※収入が年金のみの方はお申込いただけません。 |
| 必要書類 | 本人確認書類、収入証明書 |
※2023年3月期の月次データ
※申込の曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱となる場合があります。
■SMBCモビットの総評
SMBCモビットはできるだけ周囲にバレることなく借入したい方におすすめの消費者金融です。
WEB完結なら原則電話連絡・郵送物なしで申請できます。
郵送物をなしに出来れば職場や家族にバレるリスクを減らすことが可能です。
また、SMBCモビットの審査時間は最短15分で行うことができます。
※申込の曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱となる場合があります。
契約後はアプリから最短3分で振込されるため、即日融資を希望される方にも向いています。
ネットで申込した後に電話をすれば、審査をすぐに開始してくれるので、早く借入したい方はコールセンターへの電話も検討しましょう。
- SMBCモビットの審査の甘さに
関する利用者の声① - SMBCモビットの審査の甘さに
関する利用者の声② - SMBCモビットの審査の甘さに
関する利用者の声③
| 敷居が低く借りやすかった | 男性(正社員)35歳~39歳 |
|---|---|
| 総合的な満足度 | 全体的に飛び抜けた長所もないが短所もなく、比較的敷居が低いため借りやすいと思う。 |
| 借入までの早さ | すぐではなかったが必要な時に借りることはできた。 |
| 金利の低さ | 100万以下だと18.0%なので少額だと金利が高く感じる。 |
| 借入時の便利さ | コンビニや銀行振込など対応できる選択肢はある。 |
| 対応が早かった | 女性(アルバイト・パート)40歳~44歳 |
|---|---|
| 感想 | この2ヶ月で携帯会社やショッピング施設、交通系のカードとキャッシングの審査に数社、申し込んだその日のうちに落ちてしまったんですが、SMBCモビットは30分くらいで審査に通りました。 |
| カードが届いてからすぐに借入できた | 男性(正社員)50歳~54歳 |
|---|---|
| 総合的な満足度 | 買い入れ申込からカードの発行まで、インターネットで手続きが出来てかんたんだった |
| 借入の早さ | カードが届いてからすぐに借入をすることが出来た |
| 金利の低さ | 普通だと思う |
アイフルは最短18分と審査時間が早め

アイフルはカードレス取引にも対応しているため郵送なしで融資できる消費者金融です。
また、融資スピードが最短18分※でありスピード面もアイフル最大の特徴といえます。

以下で、アイフルと大手消費者金融を4社の融資スピードを比較しました。
| 消費者金融 | 融資スピード |
|---|---|
| アイフル | 最短18分※ |
| プロミス | 最短3分※ |
| アコム | 最短20分※ |
| SMBCモビット | 最短15分 |
※お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
他社に比べて5分から10分以上融資スピードがはやく最短即日融資が可能なので、急な出費が重なってしまった人や今すぐにお金が必要な人にもおすすめです。
また、女性専用ダイヤルも用意されているため、初めて消費者金融を申し込む女性にも適しています。
アイフルはスマホアプリを利用すれば、24時間365日いつでも申込が可能です。
アプリで運転免許証の読み取りを行うと、本人情報の入力にかかる時間も短縮できます。
カードレス取引にも対応しているため、家族に内緒で借りたい方におすすめです。
さらに事前に融資可能かが分かる事前診断では、最短1秒で結果が分かります。
まずは1秒診断を試す
| アイフルの基本情報 | |
|---|---|
| 融資スピード | 最短18分※1 |
| 審査通過率※ | 34.5% |
| 金利 | 3.0%~18.0% |
| 事前審査 | 最短1秒 |
| 無利息期間 | 最大30日間 |
| 申込条件 | ・年齢20歳以上62歳以下で日本国内に在住する方 (パート・アルバイトの方、及び専業主婦の方は60歳以下) ・お勤めの方で毎月安定した定期収入のある方、または、専業主婦の方 ・楽天カード株式会社または三井住友カード株式会社の保証を受けることができる方 |
| 必要書類 | 本人確認書類、収入証明書 |
※2022年4月~2023年3月の月次データ
※1申込状況によってはご希望に添いかねます。
■アイフルの総評
アイフルはできるだけ金利を抑えて借入したい方におすすめの消費者金融です。
初めてアイフルで借入を行う方はファーストプレミアムカードローンの利用で金利を3.0~9.5%に抑えられます。
消費者金融の上限金利は18.0%前後が多いため、まとまったお金を低金利で借りたい方にピッタリです。
アイフルは銀行系グループに所属しておらず、独自の審査基準を設けています。
銀行系グループとの審査基準が異なり、他社で審査が通らなかった方もアイフルなら審査に通過する可能性があるといえます。
また、最短1秒で結果が分かる事前審査もあるため、審査に通過する可能性があるか確認したい方はアイフルの1秒診断を利用しましょう。
- アイフルの審査の甘さに関する
利用者の声① - アイフルの審査の甘さに関する
利用者の声② - アイフルの審査の甘さに関する
利用者の声③
| ダメ元でも審査に通った | 女性(契約社員)40歳~44歳 |
|---|---|
| 感想 | 自分なんかどこも貸してくれないだろうと思っていました。駄目元でアイフルさんで審査を受けました。 審査結果も出るまで長いだろうし、どうせ否決だろうと半ば諦めかけてましたが、30分以内で結果が来て助けて頂きました。 |
| 書類提出した翌日に増額できた | 女性(アルバイト・パート)35歳~39歳 |
|---|---|
| 感想 | 4件借入があった私ですが、SMBC系は借入ストップの返済のみ。他社の新たな借入も続々断られ、若干申込ブラック&審査落ちまくりでしたが、ふと4件中のアイフルさんに収入証明を提出→翌日無事に増額できました。 |
| 借入しやすかった | 男性(正社員)45歳~49歳 |
|---|---|
| 総合的な満足度 | その当時は借入やすかった |
| 借入の早さ | 審査や、記入などに時間はかかったが長時間ではなかったが、審査は通りやすく借入ができた。 |
| 金利の低さ | 当時は銀行での借入より高かった。 |
| 借入時の便利さ | 困った時や緊急時の引き出しには借入やすかった。 |
中小消費者金融おすすめランキング10選!大手との審査基準の違いについても解説

中小と違う点が主に2つあります。
中小と大手消費者金融との違い
- 審査のやり方が機械ではなく人の手で行われている
- サービスが大手より劣る
大手は基本的に各社が独自の「スコアリングシステム(自動与信審査システム)」を用いて審査をおこなっています。
スコアリングシステム(自動与信審査システム)とは、申込フォームに記入した内容などを点数化して合計点数で融資可否を決定する仕組みのことで、短時間で審査結果を出せるというメリットがあります。
アイフルでもスコアリングシステム(自動与信審査システム)を導入しており、最短18分(※)で審査結果をご連絡します。
膨大な過去の個人情報データを基に行われ、大量の申込にも対応することができます。
しかしその分柔軟さには欠けており、少しでも条件を満たせないと審査に落ちてしまいます。
反面、中小消費者金融は自動審査を取り入れているところは少なく、ほとんどが人の手で行われています。
さらに来店の場合は利用者と実際にやり取りをしながら審査が行われるため、人柄なども審査の過程では重要です。
しかし中小消費者は、大手に比べて審査時間が長かったり、金利が高いと感じてしまう場合もあります。
消費者金融を選ぶ際は金利や審査基準・借入金額を確認して、自分にあった消費者金融を探すことが大切です。
融資スピードなどより審査基準の方が気になる人は中小消費者金融も含めて探すといいでしょう。
大手消費者金融は知っているけど中小消費者金融がわからない人は、以下で中小消費者金融を紹介していますので参考にしてみてください。
| 消費者金融 | おすすめポイント | 審査スピード※ | 金利 | 無利息期間 | 電話連絡 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フタバ | 他社借入があっても 借りられる |
最短30分 | 14.959%~17.950% | 最大30日間 | あり | 1万円~50万円 |
| アロー | 原則無担保・無保証で借りられる | 最短45分 | 15.00%~19.94% | なし | あり | 200万円 |
| ダイレクトワン | はじめての方は 55日間利息0円 |
最短即日 | 4.9%~18.00% | 最大55日間 | あり | 1万円~300万円 |
| フクホー | 自己破産しても 借入の可能性がある |
最短で1時間~1週間 | 7.3%~20.00% | なし | あり | 5万円~200万円 |
| アムザ | レディースローンや学生ローン プランがある |
最短即日 | 15.0%~20.0% | なし | WEB完結の場合なし | 5万円~100万円 |
| ベルーナノーティス | 14日間無利息で 何度でも利用可 |
最短30分 | 4.5%~18.0% | 最大14日間 | あり | 1万円~300万円 |
| セントラル | 創業50周年の実績が あるため安心 |
最短即日 | 4.8%~18.00% | 最大30日間 | 原則電話連絡なし | 1万円~300万円 |
| ティー・ アンド・エス |
WEBなら24時間 申込できる |
最短即日 | 15.00%~18.00% | なし | あり | 1万円~100万円 |
| ユニー ファイナンス |
債務整理から5年以内でも 融資OK |
非公開 | 12.00%~17.95% | なし | あり | 1万円~300万円 |
| ハローハッピー | 借入がまだ残っていても 申込可能 |
最短即日 (来店の場合) |
10.00%~18.00% | なし | あり | 1万円~100万円 |
※:お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。また、受付時間・申込の曜日・時間帯によっては、審査・振込が翌日以降の取扱となる場合があります
フタバなら最大金利17.95%で借入できる

フタバは最大金利が17.950%と低く設定されている消費者金融です。
昭和38年に設立された豊富な実績を持つ金融業者で初回契約者を対象の30日間の無利息期間があることが大きな特徴です。
そのため、フタバは少しでも金利を抑えて借入をしたい人におすすめです。
公式サイトにある「お借入3問診断」を利用すると、申込前に借入の可否をチェックすることができます。
「3問診断」の質問事情
- 年齢
- 年収
- 他社借入額
上記3点を入力するだけで簡単に借入可能であるかが分かるため、事前に確認しておくと安心して申し込めます。
またフタバでは、返済のタイミングや審査の相談に乗ってもらうことができます。
どうしても返済のタイミングを変更してほしいときや審査が受かるか不安なときなどは1度相談してみてはいかがでしょうか。
| フタバの基本情報 | |
|---|---|
| 審査スピード | 最短30分※1 |
| 融資限度額 | 1万円~50万円 |
| 貸付利率 (実質年率) |
14.959%~17.950% |
| 返済期間 返済回数 |
元利均等6年以内 (2回~72回)※2 |
| 保証人・担保 | 不要 |
| 申込条件 | ・20歳以上73歳以下 ・安定した収入と返済能力を持つ人 ・銀行や信販系を除く他社からの借入件数が4社以内 (5社以上でも検討可能) |
| 必要書類 | 本人確認書類、収入証明書 |
注釈
※1:お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。また、受付時間・申込の曜日・時間帯によっては、審査・振込が翌日以降の取扱となる場合があります
※2:返済期日前でも元本の一部または全部をお支払いできます
参考元:商品について
■フタバの総評
フタバは、ほかの消費者金融の審査で落ちた経験がある方におすすめしたい消費者金融です。
他の消費者金融と違って、フタバでは自社独自の審査基準が採用されています。
カードローン審査で落ちた方でも、申込内容によっては契約できるかもしれません。
またフタバでは現在、30日間の金利特典が提供されています。
期間内に融資を完済できれば、実質利息0円でお金を借りることも可能です。
借入診断や返済シミュレーションも用意されているため、初めてカードローンを契約する方にも適しています。
カードローン審査を無事通過できるか不安な方は、一度申込を検討してみてください。
アローはアプリから申し込めて最短45分で審査が完了

アローは専用アプリで申込から借入までの手続きをアプリで完結できる消費者金融で、3秒で借入可能か結果がわかる事前審査の利用が可能です。
サイト上に年齢・年収・他社での借入額を入力すると、最短約3秒で融資の可否をチェックできます。
また、WEB完結のため自宅に郵送物が発送される心配もありません。
最短45分で審査結果を確認したい人や当日中にアローで借入を行いたい方は、スマホアプリをうまく利用しましょう。
| アローの基本情報 | |
|---|---|
| 審査スピード | 最短45分 |
| 融資限度額 | 200万円まで |
| 貸付利率 (実質年率) |
15.00%~19.94%(実質年率) |
| 返済期間 返済回数 |
残高スライドリボルビング:契約日より5年(60回) 元利均等返済:最長15年以内(2~180回) ※ご相談の上、返済回数を設定します。 |
| 遅延損害金(年率) | 19.94%(実質年率) |
| 保証人・担保 | 原則不要 |
| 申込条件 | 22歳~70歳 他の貸金業者からの借り入れが年収の3分の1未満 健康保険に加入している 勤続6ヶ月以上 他社からの借り入れを滞納していない 収入証明書の提出が可能 |
| 必要書類 | 本人確認書類、収入証明書 |
参考元:アロー 商品内容
■アローの総評
アローは、アプリからの申込で郵送物が一切ない消費者金融です。
申込から借入までWEBだけで完結できるので、店舗やATMに足を運ぶ必要がありません。
また、3秒で借入可能かがわかる事前審査や返済シミュレーションができるため、事前に借入が可能なのか確認しておきたい人におすすめです。
返済日についても、毎月決まった日に返済をするのではなく、毎月5日、10日、15日、20日、25日、月末の中から選ぶことができます。
そのため、ご自身の都合に合わせて返済を進めていくことができる特徴があります。
アローはスマホで申込から融資までが最短45分で完結し、郵送物が職場や自宅に届いてほしくない人におすすめです。
ダイレクトワンは初めて契約する方なら55日間利息0円で利用できる

ダイレクトワンは初回契約時、55日間無利息特約が利用できるカードローンです。
初回借入日の翌日から55日間は、借入・返済を何度行っても利息がかかりません。
他のカードローンより特約期間が長いため、利息をなるべく節約したい方におすすめです。
ダイレクトワンの店頭窓口で手続きを行うと、最短30分※でカード発行することも可能です。
WEB申込にも対応しているため、窓口まで来店できない方でも気軽に申し込めます。
またダイレクトワンは借入残高が10万円以下の場合、毎月の返済額を4,000円から設定することが可能です。
収入が少なくて返済に回せるお金がないという方も、無理なく返済を続けられます。
特典期間の長いカードローンを探している方は、ぜひ申込を検討してみてください。
| 審査スピード | 最短即日※ |
|---|---|
| 融資限度額 | 1万円~300万円 |
| 貸付利率 (実質年率) |
4.9%~18.0% |
| 返済期間 返済回数 |
30万円以下:3年以内 (1回~36回) 30万円以上:5年以内 (1回~60回) |
| 遅延損害金 (年率) |
20.0%(実質年率) |
| 保証人・担保 | 不要 |
| 申込条件 | 20歳~69歳までの、安定した収入のある方 (主婦、パート、アルバイト、学生の方も、収入があれば可) |
| 必要書類 | 本人確認書類(2点)、収入証明書 |
参照:ダイレクトワン 公式サイト
※:お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。また、受付時間・申込の曜日・時間帯によっては、審査・振込が翌日以降の取扱となる場合があります
■ダイレクトワンの総評
ダイレクトワンは、融資を55日間で完済できる方におすすめな消費者金融です。
無利息サービス期間中に融資を完済できれば、実質利息0円でお金が借りられます。
店頭で直接申込を行うと、最短30分※でローンカードを発行することが可能です。
(申込時間などによっては対応できない場合もあります)
またダイレクトワンには、女性専用のカードローン「Lady 1st」も用意されています。
女性スタッフと相談しながら手続きできるので、初めての方でも利用しやすいです。
借入金額が10万円以下だった場合、毎月の返済額は4,000円から設定できます。
フクホーは来店で即日融資可能で大阪在住の方におすすめの消費者金融

フクホーは1970年2月に設立された、大阪市浪速区にのみ店舗がある消費者金融です。
他の消費者金融に比べて貸付限度額が高く、最大200万円までの借入にも対応できます。
最低返済額が2,000円のため、無理のない範囲で返済を進めていくことが可能です。
フクホーはセブンイレブンのマルチコピー機を利用すると、契約書類をその場で発行でき、発行した書類を店舗へ持ち込めば当日中に審査融資を受け取ることも可能です。
またフクホーにはカードローンだけでなく、借り換えローンも存在します。
借り換えローンの契約内容は、以下の通りです。
| 融資限度額 | 最大200万円 |
|---|---|
| 貸付利率 (実質年率) |
5万円~10万円未満: 7.30%~20.00% 10万円~100万円未満: 7.30%~18.00% 100万円~200万円: 7.30%~15.00% |
| 返済期間 返済回数 |
借入日から最長10年以内 2回~120回以内 |
| 遅延損害金 (年率) |
実質年率20.00% |
| 保証人・担保 | 原則不要 |
借り換えを行うと、他社での借入を一つにまとめることができます。
現在ある借金の金利を統一したい方や、返済管理にかかる手間・時間を減らしたい方にもおすすめです。
借入件数が多くて返済に苦労している方は、ぜひ申込を検討してみましょう。
| フクホーの基本情報 | |
|---|---|
| 審査スピード | 最短で1時間~1週間 |
| 融資限度額 | 最大200万円 |
| 貸付利率 (実質年率) |
5万円~10万円未満: 7.30%~20.00% 10万円~100万円未満: 7.30%~18.00% 100万円~200万円: 7.30%~15.00% |
| 返済期間 返済回数 |
借入日から最長5年以内 2回~60回以内 |
| 遅延損害金 (年率) |
実質年率20.00% |
| 保証人・担保 | 原則不要 |
| 申込条件 | 20歳以上65歳以下で定期的な収入と返済能力がある人 |
| 必要書類 | 本人確認書類、収入証明書 その他フクホーが必要と認めた書類 |
参考元:商品案内 フリーキャッシング
■フクホーの総評
フクホーは、多額の融資を借入したい方におすすめな消費者金融です。
他の消費者金融に比べて、フクホーの借入限度額は200万円と高く設定されています。
審査を通過することができれば、最大200万円の融資を借入することも可能です。
またフクホーはカードローンだけでなく、借り換えローンも取り扱っています。
人によっては借り換えを行うことで、返済時の利息を節約できるかもしれません。
複数のカードローンを一本化したい時にも役立ちます。
毎月の返済で苦労している方は、フクホーへの借り換えを一度検討してみてください。
アムザは年金受給者の方でも消費者金融に申し込むことが可能

アムザはアルバイト・パートだけでなく、年金受給者の方でも申請できるフリーローンです。
契約時の年齢が20歳以上70歳以下で、毎月一定の収入を得ている方なら誰でも申込できます。
WEB完結で申し込む場合、郵送物の発送はありません。
申し込む時間帯によっては最短即日融資も可能なため、早急にお金を用意したい時などでも役立ちます。
またアムザはフリーローンだけでなく、レディースローンや学生ローンなども利用可能です。
個人事業主向けローンなども用意されており、それぞれの目的・用途に合わせてローン商品を選べます。
年金受給者で借入を検討している方は、申込を検討してみてください。
| 審査スピード | 最短即日 |
|---|---|
| 融資限度額 | 5万円~100万円 (審査時に担当者が決定) |
| 貸付利率 (実質年率) |
15.0%~20.0% |
| 返済期間 返済回数 |
最長10年(1回~120回) |
| 遅延損害金(年率) | 年20.0%(実質年率) |
| 保証人・担保 | 原則不要 |
| 申込条件 | 20~70歳で毎月安定的な収入を得られていること |
| 必要書類 | 身分証明書、所得証明証明書、預金通帳 公共料金の請求書・ハガキなど2通(直近で住所も表示されているもの) |
■アムザの総評
アムザは、平日中の即日融資を希望する方におすすめな消費者金融です。
平日の18時までに契約完了できれば、申込日当日に融資を銀行口座へ送金できます。
店頭での申込なら、その場ですぐ現金を受け取ることも可能です。
またアムザはWeb完結で申請した場合、申込者の勤務先や自宅に電話をかけません。
契約書類の郵送などもないため、職場や家族にバレるリスクを最小限に減らせます。
周囲にバレるのが心配な方でも、安心して手続きを進められるはずです。
ベルーナノーティスは14日間無利息で何度でも利用できる

ベルーナノーティスは、14日間無利息サービスが繰り返し利用できる消費者金融です。
この無利息サービスは初回借入時だけでなく、融資完済後でも利用できます。
前回の借入日から3ヵ月以上経過していれば、再借入する際に無利息サービスを適用することが可能です。
またベルーナノーティスは、最短30分※で審査結果を確認できます。
ネット申込なら最短3分で手続きを完了できるため、即日融資を希望する方にもおすすめです。

借入希望額が50万円以下の場合、収入証明書の提出は原則必要ありません。
そのため、比較的少額での融資を考えている場合は、書類の提出に時間がかからないメリットがあります。
ベルーナノーティスカードローンを繰り返し活用していきたいと考えている方は、申込を検討してみてください。
| ベルーナノーティスの基本情報 | |
|---|---|
| 実績※ | 営業収益:138億円以上 |
| 事前審査 | 最短3秒 |
| 本審査 | 最短30分※ |
| 金利 | 4.5%~18.0% |
| 申込条件 | 20歳~80歳までの、安定した収入のある方 (アルバイト、パート、自営業者、派遣社員、学生、年金受給者でも可) ※配偶者貸付であれば専業主婦の申し込みも可能 |
| 必要書類 | 本人確認書類、収入証明書 ※ご本人様と配偶者様の本人確認書類の写し ※住民票(ご夫婦の氏名、続柄が記載されているもの) ※配偶者貸付に関する同意書 |
※:お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。また、受付時間・申込の曜日・時間帯によっては、審査・振込が翌日以降の取扱となる場合があります
■ベルーナノーティスの総評
ベルーナノーティスは、少額融資を繰り返し利用したい方におすすめな消費者金融です。
14日間の無利息サービス期間内に融資を完済できれば、実質利息0円で何度でもお金を借りられます。
即日融資にも対応できるため、急な出費が発生した時などにも便利です。
またベルーナノーティスでは、配偶者貸付制度を適用した借入も受け付けています。
以下の書類を用意できれば、専業主婦の方でも申込可能です。
- 申込者と配偶者それぞれの本人確認書類
- 夫婦の氏名、住所などが記載された住民票のコピー
- 配偶者自身の署名が入った配偶者貸付に関する同意書
公式サイトには、「3秒借入診断」も用意されています。
審査を通過できるか不安な方も、気軽に診断結果を確認できるはずです。
セントラルは平日14時までの申込で即日融資に対応可能

セントラルは、平日14時までに申込完了できれば、即日融資を受けられる消費者金融です。
またスマホ・PCからのネット申込では、契約後すぐに口座へ融資を送金できるため、今すぐにお金を借入たい人におすすめです。
自動契約機でローンカードを発行しておけば、全国のセブン銀行ATMでも借入・返済が可能です。
また店舗内に設置されているセントラルATMは、何度利用しても手数料が発生しません。
7:00~24:00まで利用できるため、早朝や夜間などの時間帯でも借入・返済を行うことができるため
ただし一部地域のセントラルATMは、営業時間が多少異なります。
借入を行う場合は、来店前に店舗・ATMのご案内を確認しておいてください。
| セントラルの基本情報 | |
|---|---|
| 審査スピード | 最短即日 |
| 融資限度額 | 1万円~300万円 |
| 貸付利率 (実質年率) |
1万円~100万円: 実質年率4.80%~18.0% 100万円~300万円: 4.80%~15.0% |
| 返済期間 返済回数 |
1万円~30万円: 最終借入日から最長3年 (1回~32回) 30万円~300万円: 最終借入日から最長4年 (1回~47回) |
| 遅延損害金(年率) | 年20.0% |
| 保証人・担保 | 不要 |
| 申込条件 | 20歳以上の定期的な収入と返済能力のある方 セントラルの基準を満たす方 (自営業、パート、アルバイトも可) |
| 必要書類 | 本人確認書類、収入証明書 |
参考元:貸付条件
■セントラルの総評
セントラルは、WEB申込可能な消費者金融を探している方におすすめな消費者金融です。
スマホ・PCさえあれば、原則24時間365日いつでも申込できます。
平日14時までに手続きを完了できた場合、即日融資にも対応することが可能です。
またセントラルは、セントラルATMを利用すると手数料0円で取引が行えます。
「借入・返済する時に無駄な手数料を払いたくない」という方にも最適です。
銀行振込やセブン銀行ATMにも対応しているため、セントラルATMがない時でも安心して利用できます。
仕事や家事が忙しくて窓口まで行けないという方は、ぜひ申込を検討してみてください。
ティー・アンド・エスは2回目以降なら電話・WEBでの即日融資にも対応できる

ティー・アンド・エスは2回目以降利用する際、電話・WEBで即日融資が受けられるカードローンです。
即日融資を受けるためには、店舗へ来店しなければならない消費者金融もあります。
しかしティー・アンド・エスなら、2回目以降はスマホからいつでも借入を行うことが可能です。
ティー・アンド・エスの店舗には、女性担当者による相談窓口が用意されています。
女性の方や初めてカードローンを利用する方でも、気軽に借金の悩み・疑問を相談することが可能です。
再度審査を受ける必要がありますが、融資の増額相談も受け付けています。
WEBや電話で最短即日融資可能なカードローンを探している方は、申込を検討してみてください。
| 審査スピード | 最短即日 |
|---|---|
| 融資限度額 | 1万円~100万円 (申込者の年収1/3にあたる金額まで) |
| 貸付利率 (実質年率) |
15.00%~18.00% |
| 返済期間 返済回数 |
1ヵ月~60ヵ月(1回~60回) |
| 遅延損害金 (年率) |
年率20.00% |
| 保証人・担保 | 不要 |
| 申込条件 | 満20歳以上69歳以下で安定収入のある方 |
| 必要書類 | 運転免許証 マイナンバーカード 住民基本台帳カード パスポート+健康保険証 |
■ティー・アンド・エスの総評
ティー・アンド・エスは、平日17時までの即日融資を希望する方におすすめな消費者金融です。
平日17時までに契約手続きを完了できれば、当日中に融資が受け取れます。
手続きはすべてメール・Webで対応できるため、わざわざ来店する手間もかかりません。
またティー・アンド・エスの公式サイトでは、「お試しご融資診断」が利用できます。
審査に不安を感じる方も、簡単に借入の可否を診断してもらうことが可能です。
初めての方でも安心して利用できるよう、女性オペレーターによるサポートも用意されています。
ユニーファイナンスはFITカードを使うとプロミスATMで借入・返済が可能

ユニーファイナンスは、FITカードを発行すればプロミスATMで取引が行える消費者金融です。
FITカードの発行は店頭・FAX・電話にて24時間受け付けており、申込手続きは最短1時間程で完了します。
無担保ローンの場合は、ホームページから申し込むことも可能です。
ユニーファイナンスは審査完了後、セブンイレブンの複合機で契約書類を発行することが可能です。
発行した契約書類を記入して返送すれば、郵送よりも短い時間で契約手続きを完了できます。
近くのプロミスATMで融資を借入したい方は、一度申込を検討してみてください。
| 審査スピード | 非公開 |
|---|---|
| 融資限度額 | 1万円~300万円まで |
| 貸付利率 (実質年率) |
12.00%~17.95% |
| 返済期間 返済回数 |
最終借入日から最長7年5ヵ月 (1回~82回) |
| 遅延損害金(年率) | 20.00%以下 |
| 保証人・担保 | 不要 |
| 申込条件 | 20歳以上の安定した収入がある方 |
| 必要書類 | 本人確認書類、収入証明書 |
■ユニーファイナンスの総評
ユニーファイナンスは、近くのプロミスATMでお金を借入したい方におすすめな消費者金融です。
FITカードを発行することで、プロミスATMで自由に借入・返済が行えます。
カードの申込は24時間受付中、手続きにかかる時間は最短60分です。
店頭で申し込んだ場合は、契約完了後にその場でカードを受け取れます。
またユニーファイナンスは、振込融資にも対応可能です。
平日14時までに契約できれば、当日中に金融機関口座へ直接融資を送金できます。
(審査結果によっては、即日振込できない場合もあります)
ハローハッピーは他社の消費者金融で借入がまだ残っている方でも申込可能

ハローハッピーは、他社での借入が残っている方でも申請できるカードローンです。
申込者の収支バランスを基準に審査してくれるため、返済状況によっては借入できる可能性があります。
審査を無事通過できるか不安な方でも、ハローハッピーなら安心して申し込むことが可能です。
ハローハッピーは店舗窓口へ来店できる場合、最短即日融資にも対応することが可能です。
Webから申込を済ませた後に来店すれば、その日のうちに借入できますのですぐに借りたい人におすすめです。
返済に関する相談も受け付けているため、初めてカードローンを利用する方にもおすすめです。
カードローン審査に対して不安を抱えている方は、申込を検討してみてください。
| 審査スピード | 最短即日(来店の場合) |
|---|---|
| 融資限度額 | 最大100万円 |
| 貸付利率 (実質年率) |
10.00%~18.00% |
| 返済期間 返済回数 |
1ヶ月~48ヶ月 1~48回 |
| 遅延損害金(年率) | 20.00%(実質年率) |
| 保証人・担保 | 不要 |
| 申込条件 | 成人以上で定期的に収入のある方 |
| 必要書類 | 運転免許証、給与明細 |
■ハローハッピーの総評
ハローハッピーは、他社での審査で落ちた経験がある方におすすめなカードローンです。
審査では信用情報だけでなく現在の経済状況を重視して借入の可否を判断してくれます。
他社では審査落ち⇩経験がある方でも、申込内容によっては契約できるかもしれません。
(審査結果によっては、ご希望に添えない場合もあります)
安定した収入さえあれば、債務整理や自己破産の経験がある方も申込可能です。
またハローハッピーは、店舗へ来店できる場合は即日融資にも対応できます。
店舗の営業時間は、平日9:30~18:00です。
大阪市在住で18時までに来店できる方なら、当日中に融資を受け取れます。
信販会社のカードローンおすすめランキング3選!独自のサービスや特徴についても解説

信販会社はクレジットカードや各種ローン商品を取り扱う企業として知られていますが、カードローンの提供行っています。
信販会社のカードローンは申込~融資までのスピードが早く、最短即日で融資が可能です。
また、信販会社ならではのポイント還元や特典プログラムなどのサービスを展開している会社もあります。
借入だけでなく、返済や日常の利用においてもメリットを享受できる仕組みが整っています。
以下では、信販会社のカードローンについて詳しく解説します。
【ドラッグすると左右にスクロールできます】
| クレジット会社 | おすすめポイント | 本審査 | 金利 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 三井住友カード | 最短5分でカードを 即時発行できる! |
即時発行で 最短5分※1 |
1.5%~14.4% | 10~800万円 |
| オリックスマネー | カードレス取引で 利用可能◎ |
最短60分 | 2.9%~17.8% | 50~800万円 |
| オリコカード | 返済プランを 2種類から選べる! |
最短当日 | 4.5%~18.0%※2 | 最大500万円 |
注釈・参照
※1:最短5分の会員番号発行は、新規契約時点でのご利用枠は50万円でのお申込みとなります
※1:最短5分の会員番号発行 受付時間:9:00〜19:30
※2:利用可能枠に応じて変動
三井住友カード カードローン(振込専用)は最短5分でカードを即時発行できる

三井住友カード カードローンは、最短5分※でローンカードを発行できるカードローンです。
発行したローンカードを使うことで、全国の銀行・提携コンビニATMで取引が行えます。
WEB申込後に銀行振込を依頼すれば、指定口座へ直接融資を送金してもらうことも可能です。
また三井住友カード カードローンには、適用金利引き下げサービスが存在します。
返済実績を積み重ねていくと、金利を年0.3%ずつ引き下げてもらうことが可能です。
最大1.2%まで引き下げできるので、利息をなるべく節約したい方に最適です。
ただし返済を遅延・延滞してしまうと、サービスは適用されなくなってしまいます。
融資の返済を期日通りに実施できる自信がある方は、ぜひ申込を検討してみてください。
| 三井住友カード カードローンの基本情報 | |
|---|---|
| 実績 | ‐ |
| カード発行時間 | 最短5分※ |
| 融資時間 | 最短翌日※1 |
| 借入利率 | 年1.5%〜14.5% |
| 申込条件 | お申込時満20歳以上満69歳以下の方 原則安定したご収入のある方 当行指定の保証会社であるSMBCコンシューマーファイナンス株式会社の保証を受けられる方 |
| 必要書類 | 運転免許証 個人番号カード パスポート 住民基本台帳カード |
注釈
※最短5分の会員番号発行は、新規契約時点でのご利用枠は50万円でのお申込みとなります
※最短5分の会員番号発行 受付時間:9:00〜19:30
※1:申込完了後の確認事項や、本人確認書類の提出状況によっては異なる場合がございます
■三井住友カード カードローンの総評
三井住友カード カードローンは、融資の返済を滞りなく継続できる方におすすめなカードローンです。
期日通りに返済を続けていけば、実績に応じた分の金利引き下げサービスが適用されます。
最大1.2%まで金利を引き下げできるので、返済時の利息を節約したい時に有効です。
また三井住友カード カードローンは、ローンカードなして取引を行いたい方にも適しています。
振込専用タイプなら、スマホひとつで借入・返済を自由に行うことが可能です。
自宅に契約書類などの郵送物が届くこともないので、家族にバレる心配もありません。
オリックスマネーはアプリ・ネットを使うことで消費者金融をカードレス取引で利用可能

オリックスマネーは、アプリによるカードレス取引が可能なカードローンです。
アプリ内の「スマホATM」を活用することで、近くのセブン銀行ATMで自由に借入・返済が行えます。
オンライン本人確認サービスを利用した場合、自宅に契約書などの郵送物が届くこともありません。
またオリックスマネーは、5つの契約コースに分けて適用金利が設定されています。

| 契約コース | 金利(実質年率) |
|---|---|
| 600万円・700万円・800万円 | 2.9%~6.0% |
| 400万円・500万円 | 5.0%~8.0% |
| 200万円・300万円 | 5.3%~12.5% |
| 100万円 | 10.0%~14.5% |
| 50万円 | 12.0%~17.8% |
参照:オリックスマネー 公式サイト
利用用途や返済プランに合わせて、契約するコースを自由に選ぶことが可能です。
ただし申込情報によっては、希望するコースが契約できない場合もあります。
家族や勤務先に内緒でお金を借りたいと考えている方は、ぜひ申込を検討してみてください。
| オリックスマネーの基本情報 | |
|---|---|
| 実績 | ‐ |
| 事前審査 | あり |
| 本審査 | 最短60分 |
| 金利 | 2.9%~17.8% |
| 申込条件 | 日本国内に居住 満20歳以上69歳までの方 毎月定期収入がある方 |
| 必要書類 | 本人確認書類 |
■オリックスマネーの総評
オリックスマネーは、なるべく早く現金を引き出したい方におすすめなカードローンです。
スマホATM取引は、アプリ型・カード発行型のどちらでも利用できます。
公式アプリ上で手続きを行えば、契約完了後にすぐ近くのATMでお金を引き出すことが可能です。
またオリックスマネーは、借入額に合わせて契約コースを自由に選択できます。
50万円コースの最大金利は年17.8%ですが、100万円コースの最大金利は年14.5%です。
契約するコースに合わせて、借入時の適用金利を引き下げられる可能性があります。
ただし希望したコースを契約できるかは、審査の結果次第です。
申込内容などによっては希望した金利が適用されない場合もあるため、申込時は注意しましょう。
オリコカードローン「CREST」は返済プランを2種類の中から選べる消費者金融
オリコカードローン「CREST」は、2種類の返済プランが用意されているカードローンです。
申込者は【残高スライド返済コース】と【定額返済コース】の中から、利用するプランを自由に選択できます。
2種類の返済プラン
- 残高スライド返済コース:利用残高に応じて毎月の返済額が設定されるプラン
- 定額返済コース:借入上限に応じて毎月の返済額を1,000円単位で設定できるプラン
【残高スライド返済コース】は、利用残高に応じて毎月の返済額が設定されるプランのため、返済額を最小限に抑えることが可能で収入の少ない方などに適しています。
【定額返済コース】は、借入上限に応じて毎月の返済額を1,000円単位で設定できるプランのため、返済額を細かく変更でき、収入が不安定な方などに向いています。

またオリコカードローン「CREST」は、融資の返済を自動引き落としで行ってくれます。
申込時に銀行口座を登録しておけば、わざわざ返済日に手続きを行う必要はありません。
毎月自動的に返済を行えるので、滞納・延滞のリスクも最小限に抑えられます。
自身の収入に合わせて毎月の返済額を設定したい方は、申込を検討してみてください。
| 融資限度額 | 最大500万円 |
|---|---|
| 貸付利率(実質年率) | 4.5%~18.0% (利用可能枠に応じて変動) |
| 返済期間・返済回数 | 1ヵ月~154ヵ月 (1回~154回) |
| 遅延損害金(年率) | 18.0%(実質年率) |
| 保証人・担保 | 不要 |
| 申込条件 | 満20才以上 安定した収入がある方 その他当社が認める方 |
| 必要書類 | 本人確認書類 |
■オリコカードローン「CREST」の総評
オリコカードローン「CREST」は、契約後の返済遅延が心配な方におすすめなカードローンです。
それぞれの収入や生活に合った返済プランを選択することで、毎月の返済負担を軽減できます。
返済方法を「口座引き落とし」に設定しておけば、うっかり支払いを忘れる心配もありません。
またオリコカードローン「CREST」には、最大2ヵ月間の利息キャッシュバック特典が用意されています。
入会日の翌月末までに借入を行うことで、入会日の3ヵ月後にキャッシュバックを受け取ることが可能です。
キャッシュバックされたお金は、申込時に登録した金融機関口座へ直接振り込まれます。
短期間の借入を希望する方にも最適です。
キャッシュレス決済型ローンのおすすめランキング!アプリで完結可能な2つについて解説

日常的にアプリでの決済を利用している方には、キャッシュレス決済型ローンがおすすめです。
アプリを通じて利用できて、スマートフォン上で簡単に管理することが出来るのが特徴です。
これによって日々の買い物や急な出費に対応することができます。
また、借入金はアプリの残高に直接チャージされるのですぐにお金を手にすることが可能です。
以下では、キャッシュレス決済型ローンについて詳しく解説します。
【ドラッグすると左右にスクロールできます】
| アプリ名 | おすすめポイント | 金利 | 融資スピード※1 | 融資限度額※2 |
|---|---|---|---|---|
| LINEポケットマネー | 申込~審査を LINEアプリ完結! |
3.0%~18.0% | 最短即日 | 300万円 |
| au PAY スマートローン |
au PAY残高に チャージ可能◎ |
2.9%~18.0% | 最短即日 | 300万円 |
注釈・参照
※1:電話による勤務先への本人在籍確認が必要となります
※2:申込状況によってはご希望に添いかねます
※3:はじめての場合30日間の利息キャッシュバックあり
LINEポケットマネーは最大100日間の支払い利息キャッシュバックが受けられる

LINEポケットマネーは、最大100日間の支払い利息キャッシュバックが受けられるカードローンです。
この特典は、初めてLINEポケットマネーを契約する方なら誰でも利用できます。
初回契約日から100日間に返済した金額のうち、利息分にあたる金額をLINE Pay残高でキャッシュバック可能です。
期間内に融資を完済できれば、実質利息0円で借入できる計算となります。
そしてLINEポケットマネーは審査が最短30分で完了するので大手消費者金融と大差がありません。
またLINEポケットマネーは、繰り上げ返済を行う時に手数料が発生しません。

LINEアプリでいつでも返済できるうえ、返済額は100円から設定できます。
それぞれの収入や返済プランに合わせて、無理なく返済を進めることが可能です。
利息を節約しながら効率的に返済していきたいと考えている方は、申込を検討してみてください。
| LINEポケットマネーの基本情報 | |
|---|---|
| 実績※ | 貸付実行額:200億円以上 |
| 事前審査 | なし |
| 本審査 | 最短30分 |
| 金利 | 3.0%~18.0% |
| 申込条件 | LINEポケットマネー加入時の年齢が満20歳から満65歳までの安定かつ継続した収入の見込める方 その他当社が認める方 日本国内在住の方 |
| 必要書類 | 本人確認書類、収入証明書 |
■LINEポケットマネーの総評
LINEポケットマネーは、借入金額や収入に合わせて契約プランが選べるカードローンです。
申込の際は、以下3つの中から契約するプランを自由に選択できます。
- 最大30日間利息キャッシュバック特典が利用できる「スタンダードプラン」
- 初回返済日が最短6ヵ月後だから無理なく返済できる「マイペースプラン」
- 55万円以上の借入を契約できた時に利用できる「プレミアムプラン」
手続きはずべてLINE上で完結できるため、職場や家族に内緒で借入することも可能です。
また、LINEポケットマネーは審査時にLINEスコアも判断材料として使用します。
LINEスコアの点数が高くなればなるほど、審査を有利に進められるでしょう。
LINE関連のサービスを普段よく利用している方にもおすすめです。
au PAY スマートローンは最短30分で審査が完了しau PAY残高にチャージできる

au PAY スマートローンは、借入資金をそのままay PAY残高へチャージできるカードローンです。
スマホさえあれば、au PAYへのチャージは原則いつでも行えます。
チャージした残高はau PAY対応の店舗だけでなく、Mastercard加盟店やコンビニでも利用可能です。
また、auPAYスマートローンは、下限金利が2.9%と他社の消費者金融に比べて低く設定されています。
そのため、auPAYスマートローンは、金利を抑えてお得に借入をしたい人におすすめです。

またau PAY スマートローンは、最短30分で審査が可能でセブン銀行を使っての借入・返済にも対応しています。
スマホ内にアプリをインストールすることで、全国のセブン銀行でカードレス取引が可能です。
ネット上で取引口座の登録を行っておくと、本人確認書類を提出することなく手続きが完了できます。
借入した融資をau PAYとして活用したい方は、ぜひ申込を検討してみてください。
| au PAYスマートローンの基本情報 | |
|---|---|
| 実績※ | 営業利益推移:60億円以上 |
| 事前審査 | あり |
| 本審査 | 最短30分 |
| 金利 | 2.9% ~ 18.0% |
| 申込条件 | 本人名義のau IDを持っている人 満20歳以上、70歳以下の人 定期収入のある人 携帯電話を持っている人 現住所が国内にある人 |
| 必要書類 | 本人確認書類(2点) |
■auPAYスマートローンの総評
auPAYスマートローンは、借入した融資をauPAYで活用したい方におすすめなカードローンです。
契約完了後は原則24時間、いつでも融資をauPAY残高へチャージできます。
チャージした残高は、全国のauPAY対応店舗で使うことが可能です。
またauPAYスマートローンは、チャージした残高を使うことでPontaポイントが貯められます。
借入しながらPontaポイントも貯めたいという方に最適です。
Pontaポイントの還元率は、利用金額200円ごとに1ポイントとなっています。
消費者金融の申込時の選び方4つ

消費者金融へ申込を行う時は、自身の要望や目的にあった消費者金融を選ぶことがとても重要です。
どの消費者金融へ申し込もうか迷っている方は、以下の選び方を参考にしてみてください。
おすすめの消費者金融の選び方
- 審査通過率が公表されているか
審査に通るか不安な人も安心 - 電話連絡なしで申込可能か
家族や職場にバレないか不安な人も安心 - 融資スピードが速いか
すぐにお金を借りられるか不安な人も安心 - 適用金利が安いか
返済時の利息が不安な人も安心
審査が甘い消費者金融はありませんが、審査が不安な人は安心して審査に挑める消費者金融を選ぶことをおすすめします。
それぞれの要望や目的に合った消費者金融へ申し込めば、借入後に後悔する心配もありません。
ここでは、それぞれの基準について詳しく解説します。
利息を抑えて借入したい時は最大金利が重要になる
消費者金融に返済する時の利息を安くおさえたい方は、最大金利がなるべく低い消費者金融へ申込ましょう。
今回紹介した消費者金融の中で、最大金利がお得なのは以下の2社です。
| カードローン名 | 最大金利 |
|---|---|
| プロミス | 年18.0% |
| オリックスマネー | 年17.8% |
カードローンの初回契約時には、最大金利での貸付が一般的となっています。
最大金利の低い消費者金融と契約できれば、返済時に支払う利息を節約できる可能性が高いです。
また消費者金融に支払う利息をより節約したい方は、契約時の借入金額にも注目する必要があります。
貸金業法が定めるカードローンの上限金利は、以下の通りです。
| 借入金額(元金) | 上限金利 |
|---|---|
| 10万円未満 | 年20.0% |
| 10万円~100万円 | 年18.0% |
| 100万円以上 | 年15.0% |
参照:5 お借入れの上限金利は、年15%~20%です|日本貸金業協会
どのカードローンでも、借入金額が100万円を超える場合の最大金利は年15%までに引き下げられます。
100万円以上の借入に成功すれば、返済時の利息をより節約することも可能です。
ただし貸金業者から借入できる融資は、総量規制によって年収の1/3までと決められています。
100万円以上の借入を申し込む場合は、最低でも300万円以上の年収が必須です。
消費者金融へ申込を行う時は、借入金額が総量規制を超えないように注意してください。
審査時間が早くスピーディーに借入できるかで選ぶ
消費者金融から早くお金を借りたい方は、審査スピードの早い消費者金融へ申込ましょう。
今回紹介した消費者金融の中で、審査スピードが早いのは以下の3社です。
| カードローン名 | 審査スピード※ |
|---|---|
| プロミス | 最短3分 |
| SMBCモビット | 最短15分 |
| アコム | 最短20分※1 |
注釈
※申込時間や審査状況によりご希望に添えない場合がございます。また、受付時間や一部金融機関の営業時間によっては、振り込みが翌営業日以降となる場合があります。
※1:お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
上記の消費者金融は、Webやスマホアプリによる本人確認を採用しています。
本人確認書類や電子証明書の写真をネット上へアップロードすることで、迅速に審査を進めることが可能です。
参照:犯罪収益移転防止法におけるオンラインで完結可能な本人確認方法の概要|金融庁
また大手消費者金融のほとんどは、振込キャッシングを使って借入できます。
各カードローンごとに利用できる金融機関は、以下の通りです。
| カードローン名 | 利用できる金融機関 |
|---|---|
| プロミス | 三井住友銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行など 【対象金融機関と振込実施時間の確認はこちら】 |
| アコム | 楽天銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行など 【対象金融機関と振込実施時間の確認はこちら】 |
| アイフル | 三井住友銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行など 【対象金融機関と振込実施時間の確認はこちら】 |
利用する金融機関によって、振込キャッシングの受付時間は異なります。
消費者金融で手早くお金を借りたい方は、申込前に受付時間をよく確認しておいてください。
審査に通りやすい消費者金融を選ぶには独自の審査基準を持つかどうかで判断する
消費者金融の審査を通過できる自信がない方は、直近の審査通過率が高い消費者金融へ申込ましょう。
今回紹介した消費者金融の中で、審査通過率を確認できたのは以下の4社でした。
| カードローン名 | 審査通過率 |
|---|---|
| プロミス | 36.9%(2024年2月時点)※1 |
| アコム | 40.6%(2024年2月時点)※2 |
| アイフル | 37.2%(2024年1月時点)※3 |
注釈
※1:SMBCコンシューマーファイナンス月次営業指標(2024年3月期2月)より参照
※2:アコム株式会社マンスリーレポート(2023年10月~2024年2月)より参照
※3:アイフル月次データ(2023年4月~2024年1月)より参照
※4:SBI新生銀行四半期データブック2023年6月末より参照
審査通過率(成約率)は、申込者全体のうち何割までが契約成功したのかを表している数値です。
審査通過率の高い消費者金融へ申し込んでおけば、審査落ちのリスクは最小限におさえられます。
それでも審査に不安を感じる場合は、独自の審査基準を採用している以下の消費者金融がおすすめです。
| カードローン名 | 運営元 |
|---|---|
| アコム | アコム株式会社 |
| アイフル | アイフル株式会社 |
| ベルーナノーティス | 株式会社サンステージ |
上記の3社は銀行などの金融機関と提携せず、自社内でカードローン審査を実施しています。
他社の審査で落ちた経験がある方も、申込内容によっては審査を通過できるかもしれません。
消費者金融の審査を無事通過したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
周囲にバレずに借りたい場合は在籍確認・郵送物の有無で選ぶ
消費者金融を家族や職場にバレることなく利用したい方は、電話連絡なしで申込可能な消費者金融を選びましょう。
今回紹介した消費者金融の中で、以下の5社は原則電話連絡なしで申請できます。
| カードローン名 | 電話連絡の有無※2 |
|---|---|
| SMBCモビット | 原則電話連絡・郵送物なし |
| プロミス | 原則なし |
| アコム | 原則在籍確認の電話連絡なし※1 |
| アイフル | 原則なし |
| レイク | なし※3 |
注釈
※1:電話での確認はせずに書面やご申告内容での確認を実施
※2:審査の結果によりお電話での確認が必要となる場合があります。
※3:在籍確認が必要な場合でも、お客さまの同意なくお電話いたしません。
カードローン申込時に申込者の勤務先や自宅へ電話をかけるのは、本人確認を行うためです。
以前までは消費者金融でも、電話で申込者の本人特定事項を確認するのが一般的でした。
金融機関等は、顧客等との間で、預貯金契約の締結等の取引を行うに際しては、運転免許証の提示を受ける等の方法により、その本人特定事項(自然人の顧客等については氏名、住居及び生年月日、法人の顧客等については名称及び本店又は主たる事務所の所在地)を確認しなければならない。
しかし現在では、書類提出と写真撮影のみで本人確認を行うのが主流になっています。
Web・スマホアプリから本人確認を行うことで、職場にバレることなくカードローンを契約することが可能です。
また一部の消費者金融は電子交付を申し込むことで、郵送物の発送もなしに変更できます。
以下のようなケースに該当しない限り、契約書などの書類が自宅に届くことはありません。
郵送物を送付するケース
ご返済の件でお客様との連絡が取れない場合
お客様が書類送付を希望された場合
当社が必要と判断した場合 など引用:よくあるご質問|アイフル
消費者金融からの電話や郵送物を避けたい方は、電話連絡・郵送物なしのカードローンをうまく活用してください。
「消費者金融」とは国から認可された貸金業者のこと

消費者金融とは、財務局から認可された貸金業者のことを指します。
ネット上ではよく「消費者金融で借りたら終わり」と言われますが、それは間違いです。
すべての消費者金融は、貸金業法・利息制限法・出資法に従ってお金を貸しています。
初めての方でも、安心してお金を借りることが可能です。
ただし消費者金融は、銀行などの金融機関に比べて適用金利が高く設定されています。
返済期間が長くなるにつれ、利息もどんどん増えてしまうため注意が必要です。
たとえばプロミスで借りた10万円を2年で完済する場合、返済総額は以下の内容になります。
| 毎月の返済額 | 元金 | 利息 | 返済総額 |
|---|---|---|---|
| 約4,982円 | 100,000円 | 19,578円 | 119,578円 |
なるべく利息を安くおさえたい場合は、早めに融資を完済させるのがいいでしょう。
また消費者金融で借りた融資の返済が遅れると、返済金額に遅延損害金が加算されてしまいます。
「消費者金融がやばい」と言われるのは、こうした返済遅延による借金の増加が主な原因です。
消費者金融での借入を考えている方は、返済期間や遅延損害金のことをよく認識しておいてください。
消費者金融は審査甘い・審査なしでは契約できない

どの消費者金融でも、カードローンを申し込む時は審査が必ず実施されます。
これは貸金業法という法律によって、申込者の返済能力や収入を調査することが義務付けられているためです。
正規の貸金業者であるかぎり、審査なしでお金を貸すことはありません。
審査なしでお金を借りたり、審査が甘いカードローンを見つけるのは不可能です。
ただし、各カードローンの審査通過率を比較すれば落ちる可能性は最小限におさえられます。
審査通過率とは、一部の消費者金融がサイト上で後悔している集計データです。
審査通過率の高い消費者金融へ申し込めば、審査に落ちる可能性は減らせます。
初めての申込で審査に不安を感じている方は、申込前に審査通過率をよく見比べてみてください。
家族・勤務先にバレずに借入することは可能

消費者金融は審査なしでは契約できませんが、電話連絡なしで申し込むことは可能です。
消費者金融が資産を行う時は原則、申込者の自宅や勤務先に在籍確認の電話をかけます。
しかし以下の消費者金融は、審査時に自宅・勤務先への電話連絡を行いません。
電話連絡なしで申し込めれば、家族や勤務先にバレる可能性はかなり軽減できます。
WEB完結に対応したカードローンなら、申込手続きもWEB上で完了させることが可能です。
銀行口座に直接送金できるため、借入する瞬間を見られてしまう心配もありません。
家族・会社に内緒でお金を借りたい方は、電話連絡なしをうまく活用してみてください。
消費者金融は警視庁でのデータ照合が不要なので即日融資に対応可能

貸金業法は、利用者の過剰債務(借入額が申込者の返済能力超えている状態)を予防するために施行された法律です。
消費者金融などの財務局長・都道府県知事から認可を得ている金融業者は、すべて「貸金業法」の対象となります。
銀行が提供するローン商品は貸金業法の対象外であるため、2017年までは即日融資に対応することが可能でした。
しかし利用者の過剰債務が増加したことによって、2018年から銀行カードローンは個人向け即日融資を停止しています。
現在銀行では審査を行う際、警察庁のデータベースで照会を行うのが義務付けられています。
迅速に手続きをすすめても、当日中に融資を受け取ることはできません。
即日融資を希望する場合は、当記事で掲載している消費者金融を活用することで解決できます。
当日中に審査結果を確認できれば、近くの銀行・コンビニATMで融資を引き出すことが可能です。
主な消費者金融の即日融資にかかる時間は、以下の通りです。
| 消費者金融 | 即日融資にかかる最短時間※1 |
|---|---|
| プロミス | 最短3分 |
| SMBCモビット | 最短15分 |
| アコム | 最短20分※2 |
| アイフル | 最短18分 |
| レイク | 最短15分融資も可能 ※3 |
注釈
※1:申込状況によってはご希望に添いかねます。お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※2:お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※3:Webで最短15分融資も可能。21時(日曜日は18時)までのご契約手続き完了(審査・必要書類の確認含む)で、当日中にお振込みが可能です。一部金融機関および、メンテナンス時間等を除きます。
一部金融機関および、メンテナンス時間等を除きます
貸金業法によって上限金利は現在15%~20%に限定されている

2000年まで消費者金融の上限金利は29.2%に設定されており、高額な利息を請求されるケースがよくありました。
しかし金利規制の見直しによって、現在消費者金融の上限金利は15%~20%に引き下げられています。
財務局長・都道府県知事から許可を得ているカードローンであれば、20%を超える金利で貸し付けを行うことはありません。
上限金利に関する記述は、出資法第5条第2項で明確に説明されています。
第五条 2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
引用元:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
出資法に違反した金融業者には、罰則が科せられます。
金利が年20%以上に設定されていた場合、その金融業者は闇金業者です。
申込先の金利が20%を超えていた場合は、別カードローンへの申込を検討してみてください。
主な消費者金融の上限金利は、以下の通りです。
| 消費者金融 | 上限金利 |
|---|---|
| プロミス | 18.0% |
| SMBCモビット | 18.0% |
| アコム | 年2.4%~17.9% |
| ノーローン | 20.0% |
| アロー | 19.94% |
消費者金融で借りたら終わり?利用する際の注意点について解説

「消費者金融で借りたら終わり?」「一度でも借りたらやばい」
先入観から不安に感じる人もいるかもしれませんが、これまで述べてきた通り消費者金融は厳格にルール化された上で国からの認可も受けているため安全です。
生活が苦しい人のなかには、毎月の給料が少ないため、消費者金融に頼らざるを得ない人もいるでしょう。
上手に利用すれば一時的な生活苦を解消できますし、貯蓄がないときの急な出費にも対応できる場合があります。
ただし消費者金融は返済の金利が銀行カードローンよりも高く設定されていることから、一時的な金欠に対応はしやすいものの、長期的にお金が必要となると不向きです。
また消費者金融の利用には全くリスクがないというわけはなく、場合によっては多重債務や自己破産といったリスクもあります。
安心・安全だからといってお金を借りすぎたり、返済を滞納してしまったりすると信頼を大きく損なってしまうことになるので絶対に避けましょう。
消費者金融でお金を借りる際は、まず自分がお金を必要としている状況が一時的なものなのか、長期的なものなのかを判断する必要があります。
その上で返済シミュレーションを利用し、毎月自分がどれだけ返済が可能か把握した上で計画的に借入を行うようにしましょう。
消費者金融カードローンは銀行カードローンより審査が甘い?法律や金利から比較

消費者金融は銀行カードローンより審査が甘いわけではありません。
消費者金融カードローンと銀行カードローンは適用される法律や金利などの貸付条件が異なります。
| 消費者金融 | 銀行 | |
|---|---|---|
| 適用する法律 | 貸金業法 | 銀行法 |
| 上限金利 | 18.0%程度 | 14.0%程度 |
| 融資時間 | 最短3分 | 最短翌営業日 |
| 審査通過率 | 公開業者あり | 非公開 |
| 無利息期間 | 提供業者が多い | 提供業者が少ない |
消費者金融カードローンは審査時間は早いため、即日融資が可能になっています。
銀行カードローンが即日融資に対応できないのは、審査時に警察庁のデータベースで反社会勢力への資金提供にならないか照会する為です。
銀行カードローンは過去に利用者数が増えるにつれ、ローン返済の遅延・延滞といったトラブルが多くなりました。
そのため審査を行う際に、申込者情報を厳しくチェックするようになりました。
また現在はどの銀行も、審査時は警察庁データベースで申込者情報を照会します。
審査結果が届くのは最短でも翌日であり、当日中に融資を受け取ることはできません。
場合によっては審査結果が届くまで、2週間以上かかるケースもあるようです。
即日融資に対応している主な大手・中小消費者金融
- プロミス
- SMBCモビット
- アコム
- セントラル
- ノーローン
「消費者金融と銀行を比較」10万円を半年間で返済する場合の利息の違い

消費者金融・銀行が提供するカードローンは、どちらも個人の方を対象にしたローン商品です。
しかし上限金利や融資限度額などの内容は、それぞれのカードローンごとに異なります。
返済総額・利息も大きく異なるため、初回申込時はシミュレーションを実施しておくべきです。
各カードローンの公式サイトには、返済シミュレーションが用意されています。
たとえばプロミス・みずほ銀行カードローンで借りた10万円を半年間で完済する場合、返済総額が安いのはみずほ銀行カードローンです。
- プロミスの返済シミュレーション結果
| 返済 回数 |
返済額 | 元金 | 利息 | 借入 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,542 | 16,059 | 1,483 | 83,941 |
| 2 | 17,542 | 16,297 | 1,245 | 67,644 |
| 3 | 17,542 | 16,539 | 1,003 | 51,105 |
| 4 | 17,542 | 16,784 | 758 | 34,321 |
| 5 | 17,542 | 17,033 | 509 | 17,288 |
| 6 | 17,544 | 17,288 | 256 | 0 |
| 総額 | 105,254 | 100,000 | 5,254 | - |
参考元:プロミス ご返済シミュレーション
- みずほ銀行カードローンの返済シミュレーション結果
| 返済回数 | 返済額 | 利息 | 借入残高 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1,166 | 101,166 |
| 1 | 20,946 | 1,179 | 81,399 |
| 2 | 20,946 | 948 | 61,401 |
| 3 | 20,946 | 716 | 41,171 |
| 4 | 20,946 | 479 | 20,704 |
| 5 | 20,946 | 241 | 241 |
| 6 | 20,704 | 2 | 0 |
| 総額 | 104,731 | 4,731 | - |
利息額をよく比較してみると、利息自体は523円しか変わりません。
金利特典の利用も考慮した場合、実際に借入するならプロミスがお得です。
また銀行カードローンは「貸金業法」ではなく、「銀行法」に従って融資を提供しています。

総量規制の対象ではありませんが、近年は利用者の過剰債務が問題視されるにつれて審査の厳格化が進んでいます。
審査を無事通過できるか不安な方は、消費者金融カードローンの利用を検討してみてください。
消費者金融と銀行カードローンの審査通過率の違い

消費者金融と銀行カードローンの審査通過率の違いは、審査通過率を公表しているかいないかです。
プロミスやアイフルなどの知名度が高い消費者金融は、マンスリーレポートや決算報告などで月ごとの審査通過率を公開しています。
| 消費者金融 | 銀行カードローン |
|---|---|
| プロミス・アコム・アイフルは |
どの銀行も審査通過率は非公開 |
いっぽう、みずほ銀行カードローンなどの銀行機関は審査に関する情報を一切公開していません。
契約者数なども非公開となっているため、審査に対して対策をとるのはとても難しいです。
こうした違いをふまえると、審査の難易度は消費者金融より銀行の方が高いと予想できます。
多重債務の抑制に向けて審査の厳格化が進んでいる現状では、銀行カードローンの審査を通過するのは難しいでしょう。
自身の収入や返済能力に自信がない方は、審査通過率が確認できる消費者金融を頼るのが安心です。
消費者金融・銀行どちらのカードローンを利用しようか迷っている方は、このことをよく覚えておいてください。
消費者金融と銀行カードローンの在籍確認や審査手順の違い

消費者金融と銀行カードローンは審査手順にはほぼ違いがありませんが、在籍確認の方法は大きく異なります。
プロミスなどの大手に分類される消費者金融は原則、書類提出などの方法で在籍確認を実施することが多いです。
| 消費者金融 | 銀行カードローン |
|---|---|
| プロミスなどの大手消費者金融は原則電話連絡なし (中小消費者金融は原則電話連絡あり) |
どの銀行でも審査時は原則電話連絡あり |
しかし銀行カードローンの場合では、自宅または勤務先への電話連絡で在籍確認をとるのが一般的です。
消費者金融でも勤務先や自宅に電話をかける場合はありますが、基本的には書類提出で代替確認を行ってくれます。
こうした違いを考慮すると、職場や家族にバレるリスクを軽減したい場合は消費者金融が最適です。
ただし在籍確認の電話をかける際、銀行と消費者金融はどちらも個人名を名乗ります。
もし銀行カードローンの申込時に電話がかかってきても、確実にバレるわけではありません。
電話連絡が原則である分、消費者金融に比べてバレるリスクが増えるというだけです。
消費者金融・銀行どちらのカードローンを利用しようか迷っている方は、こうした違いもよく覚えておいてください。
消費者金融の審査を通過して即日融資を受けるための注意点
消費者金融で融資を受けるためには法律に則って行われる審査を通過して契約手続きまで済ませる必要があります。
しかし中には審査通過率を公開している会社もあります。
どうしてもすぐに審査を通解したいという方は、審査通過率を公表している会社の中から選んでも良いかもしれません。
また消費者金融の審査はあくまでも法律に則って行われるものであるため、どの会社でも注意するべきポイントは同じです。
消費者金融の審査を通過して融資を受けるために注意するべきポイントは以下のとおりです。
消費者金融の審査を通過するためのポイント
- 収入から返済能力の確認
- 借入総額から総量規制に抵触していないか
- 信用情報に問題はないか
ここでは消費者金融の審査について何に基づいて行われているのか、必要な情報はどこで確認できるかなどを詳しく解説していきます。
消費者金融の審査や融資はとてもスピーディーなので、申込む際は予め必要な情報をすべて揃えておいたほうが、スムーズに融資を受けられる可能性が高まるでしょう。
申込み後に審査される「収入・借入総額・信用情報」のポイント

消費者金融の審査基準は、それぞれの会社ごとに異なります。
しかし融資の可否は、申込者の年収・借入額・信用情報に左右されるケースが多いです。
消費者金融で借りたお金は、1ヵ月ごとに総借入額に応じた約定返済額を金融業者へ返済しなければいけません。
その為毎月の収入が不安定な方は、毎月の返済ができない可能性があるとして、金融業者から「返済能力が低い」と判断される可能性があります。
また借入希望額を自身の収入より高く設定した場合、希望額での審査通過は難しいでしょう。
プラン通りに返済をすすめるためにも、借入希望額は必要最低限の額に抑える必要があります。
スムーズに審査を完了させたい場合は、申込前に信用情報を確認しておくことも大事です。

収入・借入額・信用情報に関する問い合わせは、金融庁のQ&Aサイトでも多数投稿されています。
審査に関して不明点などがある場合は、内容を一度チェックしましょう。
審査時は収入能力の確認が行われている

消費者金融は、安定した収入を得ている方だけが利用できる商品です。
金融業者は審査時に申込者のデータを確認し、収入状況を確認します。
借入額が50万円以下の場合は、自己申告によって借入状況を確認するケースが多いです。
しかし以下の条件に当てはまる方は、年収が証明できる書類を提出しなければいけません。
- 50万円以上の借入を希望する方
- 借入総額(他社での借入も含む)が100万円を超える方
書類提出が必要になる条件は、金融庁のQ&Aで確認可能です。
書類を提出しなかった場合、金融業者の判断によって審査に通過できなかったり、融資が減額されてしまう可能性もあります。
審査を有利にすすめるためにも、新規申込時は忘れずに書類提出を行っておきましょう。
年収を証明できる書類に該当するのは、以下の書類です。
・ 支払調書(直近の期間に係るもの)
・ 給与の支払明細書(直近の2カ月分以上(地方税額の記載があれば1カ月分)のもの)
・ 確定申告書(直近の期間に係るもの)
・ 青色申告決算書(直近の期間に係るもの)
収入証明書に該当する書類は、金融庁のQ&Aにも紹介されています。
金融業者によっては、提出書類を指定してくる場合もあるようです。
カードローンの審査を行う際は、事前に必要書類を確認しておいてください。
借入できる融資額は総量規制によって制限されている

貸金業者から借入できる融資の額は、総量規制という法律によって年収の1/3までに制限されています。
総量規制は個人が貸金業者から借入できる融資額を制限し、過剰債務を回避するための規制です。
たとえば年収300万円の方が借入を行う場合、限度額は100万円までです。
他社から100万円以上の融資を受け取っていた場合、新規借入を申請することはできません。
ただし総量規制の対象となるのは、カードローンやキャッシングなどの商品だけです。
消費者金融の審査は信用情報機関で申込者のデータ照会が必ず実施される

銀行・消費者金融が提供するカードローンは審査時、必ず信用情報機関での照会を行います。
信用情報をチェックすることで、申込者の借入状況・返済能力などを把握するのが目的です。
信用情報機関に登録されているデータには、以下の情報が記載されています。
・勤務先の商号または名称
・金融商品の契約内容
・貸付けの金額、残高、支払遅延の有無
参考元:日本貸金業協会
信用情報の中には、返済遅延などの金融事故も記録されます。
審査時に金融事故のデータが発見された場合、審査落ちとなる可能性が高いです。
過去にローン商品の遅延・延滞した経験がある場合は、申込前に信用情報を確認しておきましょう。
信用情報は、以下の信用情報機関に掲示請求を行うことで確認できます。
| 株式会社日本信用情報機構「JICC」 |
| 割賦販売法 指定信用情報機関「CIC」 |
| 全国銀行個人信用情報センター |
ただし開示請求を行う際は、本人確認書類と手数料がかかります。
各信用情報機関で必要となる書類・開示手数料は、以下の通りです。
| 請求時に必要な書類 | 開示手数料 | |
|---|---|---|
| JICC | ・運転免許証または運転経歴証明書 ・パスポート ・在留カードまたは特別永住者証明書 ・マイナンバーカード (個人番号カード) ・住民基本台帳カード(写真付) ・各種障がい者手帳 ・各種保険証 ・住民票(発行日から3ヵ月以内) ・印鑑登録証明書 (発行日から3ヵ月以内) ・各種年金手帳 ・戸籍謄本または戸籍抄本 (発行日から3ヵ月以内) ・自撮り画像 (ご自身を撮影した画像) ※上記書類のうち、いずれか2点(原本)を提出 |
スマートフォンによる開示手続き: クレジットカード一括払い(1,000円) 郵送による開示手続き: クレジットカード一括払い(1,000円) 窓口での開示手続き:現金(500円) |
| CIC | ・運転免許証または運転経歴証明書 ・マイナンバーカード (個人番号カード) ・パスポート ・写真付住民基本台帳カード ・写真付各種障がい者手帳 ・在留カードまたは特別永住者証明書 ※上記書類のうち、いずれか2点を提出 |
インターネット開示: クレジットカード一括払い(1,000円) 郵送開示: ゆうちょ銀行で発行の定額小為替証書(1,000円) 窓口開示:現金(500円) |
| KSC | ・運転免許証 ・パスポート ・住民基本台帳カード(写真付き) ・個人番号カード ※マイナンバーの通知カードは不可 ・在留カード、もしくは特別永住者証明書 ・各種健康保険証 ・福祉手帳 ・公的年金手帳 ・印鑑登録証明書 (発行日より3カ月以内のもの) ・戸籍謄本または戸籍妙本 (発行日より3カ月以内のもの) ・住民票 (発行日より3カ月以内で個人番号の記載がないもの) ※上記書類のうち、いずれか2点を提出 |
郵送開示: 定額小為替証書(1,000円) |
参考元:CIC 情報開示とは
参考元:JICC 信用情報の確認
職場への在籍確認が取れないと返済能力不備と判断される

消費者金融の申込時に金融業者・銀行が在籍確認を行うのは、申請内容に誤りがないか確認するためです。
審査で担当者の方が確認する年収・勤務期間などの情報は、申込者本人が自己申告したデータになります。
しかし申込者全員が嘘をつかずに、自身の個人情報を正しく記載するとは限りません。
人によっては審査を少しでも有利に進めようと、誇張した情報を金融してしまうケースもあります。
こうした申請内容の誤りを見抜くために行われているのが、在籍確認です。
在籍確認を完了できなかった場合、担当者に「この申込者の返済能力は信用できない」と判断されてしまう可能性が高いです。
多重債務者が増加した現在は与信審査の厳格化により、収入証明書が不要な場合でも在籍確認を行うよう進言されています。
借入希望額を少額に抑えても、在籍確認を避けることはできません。
カードローンの申込を考えている方は、在籍確認が滞りなく完了できるように注意してください。
消費者金融の審査に落ちた人の3つの理由
消費者金融の審査を受ける際に、一定の基準を満たしていない場合は借入が難しくなります。
消費者金融の審査に落ちる人には3つの理由が考えられます。
- 収入が不安定で返済能力がないと判断された
- 審査時に虚偽の申告をした
- 複数の消費者金融に同時に借入の申込をした
上記のように、収入状況や信用情報に問題があると審査落ちの可能性が高くなります。
消費者金融の審査に通るためには、審査に落ちる理由を理解して適切な対策を講じることが大切です。
そのため、収入を安定させ、正確な情報を申告し、申し込みのタイミングを工夫することで審査通過に期待が持てるでしょう。
以下では消費者金融の審査に落ちる理由について詳しく解説します。
収入が不安定で返済能力がないと判断された
消費者金融の審査では、安定した収入があるかどうかが重視されます。
収入が不安定な場合は返済能力が低いと判断されて審査に落ちる可能性が高くなります。
特に、パート・アルバイト、契約社員、フリーランスなどの方は、安定した収入を証明できなければ審査が厳しくなる傾向があります。
| 職業・雇用形態 | 収入の安定性 | 審査通過の可能性 |
|---|---|---|
| 正社員 (勤続3年以上) |
高い | 高い |
| 正社員 (勤続1年未満) |
やや高い | 普通 |
| 契約社員・派遣社員 | やや低い | 低い |
| パート・アルバイト | 低い | かなり低い |
| 個人事業主 (安定収入あり) |
普通 | 普通 |
| 個人事業主 (収入が不安定) |
低い | かなり低い |
このように、収入が安定しているほど審査に通りやすく、収入の変動が大きいと審査は厳しくなります。
勤続年数を伸ばし、収入証明をしっかり準備することで、審査に通る可能性を高めることができます。
審査時に虚偽の申告をした
消費者金融の審査では、申込者の情報を正確に申告することが大切です。
虚偽の申告をすると、信用情報機関のデータと照合されて嘘がすぐに発覚します。
| 虚偽の内容 | 審査への影響 |
|---|---|
| 収入を多く申告 | 実際の返済能力と合わず信用を失う |
| 勤務先を偽る | 在籍確認で発覚して不審に思われる |
| 他社借入を隠す | 信用情報機関で照合されてバレる |
| 延滞履歴を隠す | 既存の信用情報と矛盾して不正と判断される |
実際の収入より多く申告したり勤務先を偽ったりすると、信用できないと判断されて審査落ちとなります。
たとえ故意でなくても、誤った情報を申告すれば「信用できない人物」と見なされる可能性があります。
虚偽申告が発覚すると、今回の審査だけでなく、将来的な金融取引にも悪影響を及ぼすことを理解しておきましょう。
複数の消費者金融に借入の申込をした
短期間に複数の消費者金融へ申し込むと、「申し込みブラック」とみなされ、審査に通りにくくなります。
信用情報機関には申込履歴が一定期間記録され、金融機関は「資金繰りが厳しい」「返済能力に問題がある」と判断します。
その結果、審査が厳しくなり借入が難しくなります。
| 状況 | 金融機関の判断 |
|---|---|
| 1社のみの申込 | 通常審査 |
| 短期間に2~3社申込 | 返済能力を疑われて審査の厳格化 |
| 4社以上の申込 | 申込ブラックと判断される |
さらに、審査に落ちた履歴も信用情報機関に記録されます。
この情報は消費者金融だけでなく、クレジットカード、携帯電話の分割払い、住宅ローンの審査にも影響を与えます。
むやみに複数の金融機関へ申し込むのは避け、慎重に選んで申し込むことが大切です。
消費者金融は一度でも借りると危険?やばい業者を回避するために注意すべき3つのポイント
消費者金融へ申込を行う時は、正式に貸金業の登録が行われているか確認することも大切です。
消費者金融の中には、無登録で融資を行う闇金・違法業者も多く存在します。
安心して消費者金融からお金を借りたい方は、以下の3点に注目しましょう。
消費者金融の信頼性がわかる3つのポイント
- 取引実績の豊富さ
- 金融庁に登録されている貸金業者か
- 借入シミュレーションを利用して本当に借入可能か確認する。
闇金や違法業者は法外な利息を請求されたり、脅迫まがいの取り立てを受ける危険性が高いです。
参考元:違法な金融業者にご注意!
これから消費者金融へ申込を行う方は、十分注意してください。
ここでは、それぞれのポイントについて詳しく解説します。
被害を回避するには、豊富な取引実績を持つ正規の金融業者から借入する

取引実績が豊富な消費者金融
- プロミス
- アイフル
- フクホー
- SMBCモビット
- セントラル
違法な貸金業者と思われる会社は金融庁の公式サイトで公開されているので、申込前に確認しましょう。
また申込先を選ぶ際は、審査時間と金利もよく確認しておく必要があります。
即日融資可能な消費者金融を選んでおくと、手続きにかかる時間や手間を減らすことが可能です。
金利が低いカードローンを契約しておけば、支払う利息も最小限に抑えられます。
審査スピードと金利を重視する方は最短即日融資が可能なプロミスかアイフルの利用を検討してみて下さい。
| カードローン | 年間申込者数 | 審査スピード※ | 上限金利 |
|---|---|---|---|
| プロミス | 504,350人 | 最短3分 | 18.0% |
| アイフル | 436,875人 | 最短18分※ | 18.0% |
| フクホ― | 未公開 | 最短即日 | 20.0% |
※2021年4月~2022年3月の1年間のデータ
※申込状況によってはご希望に添いかねます。
※18,19歳の方は契約に至りづらい可能性がございます。また、収入証明書のご提出が必要になりますので、ご準備をお願いいたします。
消費者金融は金融庁に登録されている貸金業者から選ぶ

「消費者金融を利用したいけど、詐欺などの被害にあわないか心配・・・」という方は、一度金融庁に掲載されている情報を確認してみましょう。
貸金業法第3条により、貸金業を取り扱う会社は登録を行う必要があると定められています。
第三条 貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
引用元:貸金業法 第三条
登録が完了した後も貸金業を継続していく場合は、3年ごとに登録の更新が必要です。
また金融庁が公開している貸金業者登録一覧には、貸金業法に従って融資を行っている金融業者の登録番号・所在地などが記載されています。
財務局長・都道府県知事から認可を得ている貸金業者なら、法外な利息を請求されたりする心配はありません。
ただし闇金業者によっては、サイト上に架空の登録番号を記載しているケースもあります。
登録番号の真偽を確認したい場合は、登録貸金業者情報検索入力ページで一度調べてみるのが有効な手段です。
消費者金融を初めて申し込む際は、登録番号が記載されているか確認しておいてください。
都道府県の貸金業担当課、もしくは財務局に問い合わせるのも有効です。
【貸金業者登録されている主な消費者金融】
| 消費者金融 | 登録番号 | 登録年月 | 住所 |
|---|---|---|---|
| プロミス | - | 令和5年1月20日 | 東京都江東区豊洲2-2-31 |
| アイフル | 近畿財務局長(14) 第00218号 |
令和5年3月30日 | 京都府京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 |
| フクホ― | 大阪府知事(6)第12736号 | 令和4年3月12日 | 大阪市浪速区難波中三丁目9番5号 福宝ビル |
| SMBCモビット | HPを参照ください | 令和4年3月30日 | 大阪府大阪市中央区今橋4-5-15 |
| エイワ | 関東財務局長(14) 第00154号 |
令和4年3月1日 | 神奈川県横浜市西区平沼1-7-12 |
| キャネット | 近畿財務局長(5) 第00813号 |
令和3年1月20日 | 京都府京都市下京区黒門通四条下ル下リ松町158番地タワード四条1階 |
参考資料:財務省関東財務局「貸金業者登録一覧」
※当サイトで紹介している消費者金融は貸金業者登録のある、金融庁に認められた消費者金融です。
返済シミュレーションを行い、本当に借入可能か確認する

消費者金融でお金を借りた場合、どれくらいの負担になるのかをシミュレーションしてみたいと思います。
ここでは、一般的に適用される金利「実質年率18.0%」で、5万円と10万円をそれぞれ借りた場合でシミュレーションしてみます。
<5万円を3ヶ月で返済する場合>
| 返済回数 | 総返済額 | 利息充当額 |
|---|---|---|
| 3回 | 51,481円 | 1,481円 |
<10万円を1年間で返済する場合>
| 返済回数 | 総返済額 | 利息充当額 |
|---|---|---|
| 12回 | 109,218円 | 9,218円 |
上記のとおり、5万円を3ヶ月で返済した場合の利息の負担額は1,481円です。
10万円を1年間で返済すると利息は9,281円と、1万円に近い金額になることがわかります。
消費者金融でお金を借りる場合は、本当にやむを得ない理由なのかどうかをきちんと見極めて、できるだけ少額を借りて最短で返済するように心がけましょう。
職業や属性ごとにおすすめの消費者金融を一覧で解説!

消費者金融から申込先を選ぶ時は、自身の属性情報(職業や年齢など)に合わせてカードローンを選ぶとよいでしょう。
それぞれの属性情報ごとにおすすめの申込先は、以下のように分けられます。
| 属性 | 借入方法 | 消費者金融 |
|---|---|---|
| パート・ アルバイト |
消費者金融 (安定した収入がある方なら申込可能) |
プロミスやアコム |
| 専業主婦 | 配偶者貸付で借入できるカードローン | ベルーナノーティスや銀行カードローン |
| 学生 | 学生でも借入可能な消費者金融 (18歳以上で高校生以外の方なら申込可能) |
プロミスや銀行カードローン |
| 無職 | 質屋や国の貸付制度などを利用する | 金融機関以外の方法 |
| 審査落ちが不安な人 | 審査通過率の高いカードローン | プロミスやアコム |
| 職場や家族にバレたくない人 | 在籍確認(電話連絡)なし・郵送物なしで申込可能な消費者金融 ※電話での確認はせずに書面やご申告内容での確認を実施 |
アコムやSMBCモビット |
| 他社の借入がある人 | おまとめローン (複数の借金を一本化できる) |
プロミスやアイフル |
参考元:職業・属性別借入先一覧
消費者金融といっても、貸付内容や申込条件などは各カードローンごとにバラバラです。
そのため申込時はさまざまなカードローンを比較し、自身の属性に合ったカードローンを選ぶ必要があります。
消費者金融でお金を借りたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
ここでは、それぞれの属性ごとにおすすめな消費者金融を紹介します。
パートやアルバイトの方でも安定した収入があれば消費者金融で借入可能

パートやアルバイトの方にも消費者金融がおすすめなのは、返済能力の証明ができれば借入できる可能性が高いためです。
消費者金融の多くは、貸付条件に「安定した収入があればパート・アルバイトでも申込可能」と記載しています。
Q アルバイト(パート)・派遣社員・主婦(主夫)も契約できますか?
A はい。20歳以上の安定した収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方であればご契約いただけます。
パートやアルバイトによる収入が少ない方でも、収入の大きさは関係ありません。
毎月の収入が一定であれば、誰でも申込できます。
個人が消費者金融から借入できる金額は、貸金業法によって年収の1/3までと決められていいます。
借入希望額を年収の1/3以上にあたる金額で申請してしまうと、審査で落とされる可能性が高いです。
パートやアルバイトでお金を借りたい方は、十分注意しておいてください。
おすすめ消費者金融
パートやアルバイトの方にはプロミスやアコムなどの大手消費者金融!
プロミスやアコムは消費者金融の中でも審査通過率が高く最短3分融資が可能!
専業主婦は配偶者貸付に対応しているカードローンがおすすめ

配偶者貸付で借入可能な消費者金融を専業主婦におすすめするのは、総量規制に関係なく借入できるからです。
配偶者貸付とは、総量規制の除外貸付に分類されます。
配偶者の同意を得る必要がありますが、借入本人と配偶者の収入を合算して、その3分の1までの借入れを可能とする「配偶者貸付」という総量規制の「例外」制度があります。
配偶者貸付で借入できる金額は、夫婦が得ている合計年収の1/3までです。
専業主婦で本人に収入がない場合でも、夫に安定した収入があれば申込できます。
ただし、配偶者貸付で借入する場合は4つの書類が必須です。
申込時には、以下の書類を提出しなければいけません。
- 配偶者の収入を証明する書類
- 夫婦間の身分関係を証明する公的書類(住民票・戸籍抄本など)
- 配偶者貸付を締結することについての配偶者の同意書
- 指定信用情報機関への信用情報の提供などに関する配偶者の同意書
書類が不足していたり、内容に不備が合った場合は融資を断られてしまいます。
専業主婦でお金を借りたい方は、申込前に提出する書類の内容をよく確認しておいてください。
おすすめ消費者金融
専業主婦の方にはベルーナノーティスや銀行カードローン!
ベルーナノーティスは専業主婦でも借りれるローンや女性ダイヤルが利用可能!
学生でも18歳以上なら金融機関で借入ができる

消費者金融が学生にもおすすめできるのは、18歳以上で安定した収入があれば申込可能だからです。
令和4年に成人年齢の引き下げが行われたことで、一部の消費者金融は18歳以上から契約できるようになりました。
民法の改正により、令和4年4月から成年年齢が18歳に引き下げられ、親の同意を得ることなく、有効な貸付けの契約を締結できるようになります。
ただしほとんどの消費者金融では、高校生は申込の対象外となっています。
主婦・学生でもアルバイト・パートなど安定した収入のある場合はお申込いただけます。ただし、高校生(定時制高校生および高等専門学校生も含む)はお申込いただけません。
安定した収入があるとしても、高校生以上の学生でなければ審査は受けられません。
どうしてもお金を借りたいのであれば、学生ローンなどの方法を利用するのがおすすめです。

一方で大学生や専門学生の場合、アルバイトやパートによる安定収入があれば誰でも申込できます。
保護者の同意書なども必要ないため、家族にバレることなくお金を借りることも可能です。
ただし審査の段階で、学生は社会人よりも返済能力が低いと判断される場合もあり、審査落ちという結果になってしまうことがあります。
そのため学生が消費者金融を利用する場合には注意が必要です。
下記に大分大学が発表した、平成27年度「学生生活の実態調査結果」をご紹介しています。
この資料を見ると「家からの仕送りが5万円未満」と回答した学生は全体の72.7%となっており、前回調査と比較して3.0%増加していることがわかります。
給付額が5万円未満の割合で比較すると,前回が69.1%,今回が72.7%であり,家庭からの給付額は前回より少なくなっている。
収入が十分にない状態で消費者金融を利用すると、最悪のケースでは返済不能に陥り自己破産などの政務整理に至る場合もあります。
やむを得ず学生が消費者金融カードローンを利用する場合は、必要最小限度の金額を借りましょう。
おすすめ消費者金融
大学生以上の学生にはプロミスや銀行カードローン!
プロミスは消費者金融の中でも金利が2.5%~18.0%と低めでお得!
無職は消費者金融などの金融機関からお金を借りることはできない

無職の方に消費者金融をおすすめできないのは、カードローン審査で確実に落とされてしまうためです。
消費者金融などの金融機関は貸金業法に沿って審査を行い、申込者の返済能力に合わせて貸し付けを行っています。
全ての借入れについて、①借入れの際の返済能力の調査義務、
②返済能力を超える貸付けの禁止
無職だと「収入がない=返済能力がない」と判断されてしまうため、審査を通過することはできません。
そのため無職でもお金を借りたいと考えている方は、金融機関以外の方法に頼るのがおすすめです。
以下の方法なら、無職で収入が全くない方でもお金を借りられます。
質屋にブランド品や貴金属などを持ち込む - 加入している保険会社の契約者貸付制度を利用する
- ゆうちょ銀行の貯金担保自動貸付を利用する
質屋は担保となる品物さえ用意できれば、誰でも審査なしで利用できます。
生命保険などに加入している方は契約者貸付制度を使うと、将来の保険金を担保にして借入することが可能です。
ゆうちょ銀行に預金がある方は、貯金担保自動貸付を使うことでお金が借りられます。
無職だけどお金を借りたいと考えている方は、ぜひ一度利用を検討してみてください。
はじめてお金を借りる人は審査通過率の高い借入先から選ぶ

初めて消費者金融からお金を借りる方は、審査通過率がなるべく高い消費者金融へ優先的に申し込むのがおすすめです。
確認してみたところ、以下の消費者金融では審査通過率が公開されていました。
| カードローン名 | 審査通過率(成約率) |
|---|---|
| プロミス | 42.3%(2023年4月時点) ※SMBCコンシューマーファイナンス月次営業指標より参照 |
| アイフル | 39.2%(2023年9月時点) ※アイフル月次推移より参照 |
| アコム | 39.9%(2023年4月時点) ※アコム株式会社マンスリーレポートより参照 |
審査通過率は申込者全体のうち、どれくらいの人が借入できたのかを表す数値です。
審査通過率が高くなればなるほど、審査で落ちるリスクは減っていきます。
ただし審査通過率が高いカードローンへ申し込んでも、確実にカードローンを契約できるわけではありません。
契約できるかどうかは、申込者の返済能力や属性情報の内容次第です。
あくまでも、申込先を決める目安の一つとして考えておきましょう。
初めて消費者金融を申し込む方は、ぜひ参考にしてみてください。
おすすめ消費者金融
初めての借入の方にはプロミスやレイク!
初めての借入の場合、プロミスは借入日の翌日から無利息期間が適用される!
レイクは365日間利息ゼロ円で借りられる!
職場や家族に借入がバレたくない人は電話連絡と郵送物なしの消費者金融を利用する

消費者金融が職場や家族にバレたくない方にもおすすめなのは、自宅や勤務先への連絡を回避できるからです。
アイフルなどの大手と称される消費者金融は原則、審査時に申込者の勤務先へ電話をかけません。
お申込みの際に自宅・勤務先へのご連絡は行っておりません。
在籍確認が必要な場合でも、お客様の同意をいただかない限り実施いたしません。
アプリやWebを活用すれば、契約書などの書類もすべてメール・Web上で確認できます。
職場や家族にバレないか不安という方も、消費者金融なら安心して申し込むことが可能です。
ただし、返済を遅延・延滞した時に送られれる督促の郵送物や電話は回避できません。
職場や家族にバレたくないのなら、毎月の返済期日は必ず守る必要があります。
どうしても返済が遅れてしまう場合は、事前に相談窓口へ連絡を行っておくとよいでしょう。
家族や職場に内緒でお金を借りたい方は、返済遅延に十分気をつけてください。
おすすめ消費者金融
借入がバレたくない人はSMBCモビットやアコム!
SMBCモビットやアコムなどの大手消費者金融は在籍確認(電話連絡)が原則なし!
※電話での確認はせずに書面やご申告内容での確認を実施
2社以上の複数借入がある人は借入先を1本にするおまとめローンがおすすめ

2社以上の消費者金融で借入している方におまとめローンがおすすめなのは、毎月の返済負担と滞納リスクを軽減できるからです。
たとえば消費者禁輸3社から10万円ずつ借りて1年間で完済する場合、毎月の返済額や返済総額は以下のようになります。
| 1ヵ月ごとの返済額 | 返済総額 | |
|---|---|---|
| A社(適用金利18.0%) | 9,167円 | 110,011円 |
| B社(適用金利17.8%) | 9,158円 | 109,894円 |
| C社(適用金利19.0%) | 9,263円 | 111,156円 |
3社から借入していた場合、毎月の返済額は合計27,588円です。
返済総額は331,061円で、約31,000円の利息を支払う結果になります。
しかし3社の借入額30万円をおまとめローンで一本化した場合、毎月の返済額・返済総額は以下の通りです。
| 1ヵ月ごとの返済額 | 返済総額 | |
|---|---|---|
| おまとめローン | 27,475円 | 329,701円 |
1年間で30万円を完済する場合、毎月の返済額は27,475円になります。
返済総額は329,701円と、3社で借入していた時よりも1,360円安くなる結果となりました。
毎月の返済回数も3回から1回に減るため、うっかり返済を忘れてしまうリスクも軽減することが可能です。
返済期間や適用金利などによっては、契約前より返済額が増えてしまうケースもあります。
毎月の返済負担や利息を節約するには、申込前におまとめローンの貸付条件をよく確認しておくことがとても大事です。
おすすめ消費者金融
2社以上の借入がある方はプロミスやアイフルのおまとめローン!
プロミスやアイフルのおまとめローンは金利が低く、即日融資に対応可能!
借入理由が一時的な借入以外は、消費者金融を利用しない

消費者金融の使い方によっては以下のようなリスクが存在します。
| ①借りすぎによる多重債務 | 3~5社以上の消費者金融から借金をしてしまい、返済できない状態になる |
|---|---|
| ②返済困難により信用情報に傷がつく | 信用情報に傷がつくと借入がしずらくなる |
| ③自己破産 | 自己破産し、家や財産を失う |
上記であげたリスクについて、もう少し具体的な数字から消費者金融を利用するリスクについて見ていきましょう。
①の「借りすぎによる多重債務」について、全国の消費生活センターに寄せられた多重債務に関する相談は、直近の平成29年度で25,000件も寄せられています。
「ギャンブルが原因で5社から借金をしている。多重債務の法律相談を受けたい」といった、賭け事が原因での多重債務問題も深刻化しています。
②の「返済困難により信用情報に傷がつく」は消費者金融だけでなく、その他ローンにも影響する可能性があります。
クレジットカードの発行などにも影響する可能性がありますので、返済困難になる額の借入には気を付けましょう。
③の自己破産者については、すべてが消費者金融の利用者ではないにしても、平成29年度には年間68,792件もの自己破産事件が申請されています。
上記のデータが書かれている資料のなかには、「多重債務者が借金をしたきっかけ」に関するデータもあります。
多重債務に陥った人の「借金をするきっかけ」をみると、収入の減少のほかにギャンブルや商品の購入など、借金せずに済んだのでは?と思われるような内容も含まれています。
ギャンブルが原因で借金をしてしまうと、「ギャンブルで勝って完済できるはず」と、根拠のない理由からさらに借金を重ねてしまうことがあります。
やむを得ず消費者金融を利用する場合は、一時的な借入にとどめるようにしましょう。
審査が甘い消費者金融についてよくある質問
審査甘い消費者金融についてよくある質問と回答を紹介します。
Q.土日でも利用できますか?
Q.専業主婦でも利用できますか?
大手・または中小消費者金融の利用を検討する際は、単に「審査が甘い」ところを探すのではなく、自身の財務状況に合った適切な借入先を選ぶことが大切です。
また、借入前に複数の消費者金融を比較し、金利や返済条件などを十分に確認するこようにしてください。
次項から、1問ずつ詳細に解説していきます。
最も審査が甘い消費者金融はどこですか?
厳密には審査が甘い消費者金融は存在しません。
全ての消費者金融は、貸金業法に基づいて審査を行っているためです。
ただし、審査通過率が比較的高い消費者金融としては、プロミスやアコム※が挙げられます。
上記のような大手消費者金融は、豊富な実績とデータに基づいた審査システムを持っているため、適切な与信判断が可能となっています。
中小消費者金融は審査通過率が非公開の場合が多いですが、大手消費者金融の審査に通過しなかった場合の選択肢として利用されることが多いようです。
※アコムは「はじめてのアコム」というように一社目のカードローンに選ばれることが多いので審査通過率が高いようです。
土日でも利用できますか?
多くの大手消費者金融では、土日でも利用可能です。
例えば、プロミスでは土日、更に祝日でも借入が可能です。
さらに24時間申込みが可能なため、急ぎの場合でもWebからその場で申込みができます。
ただし、中小消費者金融の中には土日対応していない場合もあるので、中小消費者金融を利用したい場合は事前に確認が必要です。
いつまでに資金が必要なのかスケジュールを逆算し、余裕を持って申込できるように各消費者金融の対応可能日を調べておきましょう。
専業主婦でも利用できますか?
専業主婦の方も利用できる消費者金融はありますが、条件が厳しくなる傾向があります。
中小含む多くの消費者金融では、安定した収入があることが審査の重要な基準となっているためです。
安定した収入を得ていない専業主婦の場合、配偶者の同意が必要だったり、配偶者の収入証明が求められたりすることがあります。
借入限度額が低くなる可能性もあるため、各消費者金融の申込条件を予め確認しておくことが重要です。
また、一部の消費者金融では「配偶者貸付制度」を利用することで、専業主婦でも借入が可能になります。
この制度では、夫婦の収入を合算して審査を行います。
ただし、この制度を利用するには配偶者の同意が必要となるため、夫に内緒で借入することは困難です。
お金を借りたいなら消費者金融がおすすめ!審査は甘くないが安全に借りられる
これまで消費者金融について詳しく解説しました。
結論から言うと、消費者金融は金融庁に登録されたやばくない貸金業者であり、今すぐお金を借りたい人にピッタリです。
また、はじめて消費者金融を申し込む際は以下のポイントをチェックして消費者金融を選びましょう。
消費者金融の申込でチェックするポイント
- 消費者金融ごとの信頼性
- 審査時間
- カードローンの上限金利
よく内容を確認せずに消費者金融を契約してしまうと、闇金業者などの被害にあう危険性が高いです。
収入に見合わない借入を行うことで、過剰債務を誘発してしまうリスクもあります。

これから始めて消費者金融を申し込む方はここで解説した知識を活用し、自身の目的・用途に合った消費者金融を申し込んでみてください。